2006�N10���P���i���j�@��30����
�@���̎��{�A��v����ъč���
�@���̔��ȓ_�Ȃǂ̂܂Ƃ�
�@���s��2006�O�d�����s�ψ���̍���ɂ���
2006�N�X��10���i���j�@��29����
����F�F�u�k���e�[�͂Ȃ��ɐ���I���v
2006�N�W��20���i�y�j�@��28����
�@���̂��荇�킹
�@���W�����̑ł����킹
2006�N�V��29���i�y�j�@��27����
�@���̂��荇�킹
�@���W�����̑ł����킹
2006�N�U��17���i�y�j�@��26����
�@�ɐ������j��������
�@���̂��肠�킹
�@���֘A�������ɂ���
2006�N�T��13���i�y�j�@��Q�T����@
�P�@���C���w�R�[�X�̌����i���n������j
���яr�V����i�㔼�ɐΕ������j�̈ē��ɂ��A�k�����ِՁE�Z�c�ِՁE�Z�c�n��A�����@�ՁE�y�䉫�n��̌��w�B�R�[�X�́A���̊T�����̂悤�ɂȂ����B�Ȃ��A�J�V�ł���{�I�ɂ͓��R�[�X��������ƂƂ����B�Ȃ��A���̉w���ɗ]�T������A�����@�Ղɂ�������邱�ƂƂ����B
12:50�@�@�@�@�@�@14:20�@�@�@�@15:00�@�@�@ 15:15�@�@�@�@15:30�@�@�@�@�@�@�@�@�@15:45
�{���o�X���k���_�Ё��Z�c�ِՁ��Z�c�n�恨�����n��i�X���j���y�䉫�n��
�@�@�@�@�@�@�@�@16:00�@�@17:30
�i���̉w�j���i�o�X�j���ÐV���w�@�@
�Q�@���J�ÂɊւ��鏔����
�E
�ē���A���A�o�X�A�����W�ȂǂɊւ���ł����킹�B
2006�N�S��15���i�y�j�@��24����
�P�@���̂��荇�킹
�E
�U���ɑ��҂̍쐬�����������܂߂��ł����킹�����{���邱�ƂƂȂ����B
�Q�@���Z�ÁE��g�c���w�R�[�X�̌���
�E
�{���P�Q�F�T�O�����Z�Ái腖����t�߁j����Õ��c�遨��g�c�������i�P�U�F�S�T�܂Łj���Éw�i�P�V�F�P�O���j�Ƃ����s���Ƃ����B
�R�@���J�ÂɊւ��鏔����
�E
�o�X�A���e��A���A�����A�J�Òʒm�ȂǂɊւ���ł����킹�B
�E �w�k�����Ƃ��̎���x�i��25��O�d�������������W�j�ւ̋��͂ɂ��āB
2006�N�R��25���i���j�@��23����
���Z�ÁE��g�c���w�R�[�X�̌���
 �@���̗��ł́A������ڌ��w�R�[�X�̂ЂƂł�����Z�È�g�c�R�[�X�̌��n��������s�����B �@���̗��ł́A������ڌ��w�R�[�X�̂ЂƂł�����Z�È�g�c�R�[�X�̌��n��������s�����B
�@���Z�Âł́A�Îs���R�Ë��n������A�������E�s�n���P�_�Ђ��o�ē��}����ʂ鋌�Q�{�X���̔����_�{�Q���O�܂ł�������B�ߑ�̎Q�{�X�������̕���͂��Ȃ莸���Ă���A�ꕔ�ɂ��̖ʉe���c��ɉ߂��Ȃ��B�n�`�́A���Ă̊��Ε����̌E�n���킸���Ɋm�F�ł��邪�A���Ȃ薄�ߗ��Ă��i�s���Ă���B�s���Ƃ��āA�����_�Ёi����_�Ёj���牋�����܂ł̊Ԃ�������ǂ�������������K�v������B
�@��g�c���w�R�[�X�ł́A��C������������c�_�Ђ��o�Ď�������т�������B�����݂̕���͎c����Ă��邪�A�����͂��߁A��͂���ς������ȂƂ���������B�������암�̈�т�����A���͔̏�r�I�m�邱�Ƃ��ł���B
�@�s���Ƃ��ẮA���Z�Â����g�c�����邱�ƂŁA�����݂̈Ⴂ�͎����ł�����̂Ǝv����B�܂��A��g�c�̈ʒu���m�F���邽�߁A��Õ��c��Ղɓo��Ƃ����Ă���������ɒl���悤�B
2006�N�Q��19���i���j�@��22����
���c���r�u��g�c�𒆐S�Ƃ������ߐ��ڍs�����c�h��k�c�̍\���ƓW�J�ւނ��āv
��g�c�����Ǝ��O�ɂ���
�@�u��g�c�𒆐S�Ƃ������ߐ��ڍs�������c�h��k�c�̍\���ƓW�J�ւނ��āv�Ƃ�����(060215�j�ƈ�g�c�����̈ē�(040311)���s�������A���e���č\�����⑫����ƈȉ��̇T�`�V�ƂȂ�B
�T��g�c�����Ɛ�C�����c
�@��g�c�����͐퍑�����炻�̒[�����F�߂���W���ł���B�������Ȃ���]�ˊ������˂ɂ���Ď����͊g������Ă���A����ȑO�̎p�͎j�����R�����������邱�Ƃ͔��ɓ���B�]���A�����̌i�ς��l�@����肪����Ƃ��č��܂Ŏg�p����Ă����̂́A�P�n������߂�����j�n���I�l�@�A�Q�w���p���L�x�̋L�q�A�R��C���̐e�a�M�̒��S�����e�����ݎ��A���̌������߂����đO���A���A�����ˎ�̂������ł����Ȃ�ꂽ�����L���ꂽ��������A�S���c�_�Ђ̈ʒu�A�ł������B�����������A�j���I����̑傫���Ȃ������ߎO���ɂ���đ��푽�l�ȃA�v���[�`���A���݂��Ă����̂ł���B
�@����͎����ɑ��݂������@���𖾂炩�ɂ��A�����̈�g�c���������l�@����肪�����lj��������ƍl����̂ł���B�g�p����j���́A���łɕ����ߎO���ɂ���ďЉ��Ă���A���a�X�N�i1623�j�`�������N�i1661�j�̏o�ƎҁA��C�����̈ʊK�̏��i���L������C���o�ƏO���ł���B���̏o�ƏO���̎����ƌ������@�̎����A���̈ʒu�����ꂼ��l���m�肳�����B���̃f�[�^����A�������N�i1658�j�ȑO�Ɉ�g�c�������ɑ��݂������Ƃ��m�F�ł��鎛�́A�������E���іV�E�ʕۉ@�E�}�ڎ��E���q�@�E��Ɖ@�E�@���@�E�q�d���@�A�����@���������Ȃ��V��͑P��E�{���E���o�E�����i�e�q�ƍl��������̂͏������j�ł������B���̓��A���q�@�͐퍑���̌ËL�^�i�w���p���L�x�j�ɓo�ꂷ��B�����́A�֓�����̈ړ]�`���������@�i�@�Ɗi�j�A��g�c���ӂ̎��@�A�͋ȌS����̈ړ]���@�ɂ���č\������Ă���B�w���p���L�x�ɂ͑��Ɍ������Ⓑ���Ό��A�����ዷ��A�����@�E�q��A�_�������A�����^��Y�A�����V�O�Y�A�_�Z�A���҂Ȃǂ̎����w���o�ꂷ��B�܂�A����炪�j���ォ�畂���яオ�����́A�����˂ɂ��g��ȑO�̈�g�c�����̍\���v�f�ł���B���ɁA�����ȊO�ɑ��݂��閖�����Q�W���鋒�_�Ƃ��Ă̖{�R�����A���̏o�ƏO�����疾�炩�ɂ����B���̎����̍��c�{�R�Ɍ��W�����喖�́A�S���I�ɂ݂�ƁA�ɉꍑ1�i�ȉ������͏o�ƏO���ւ̓o��A�d�����܂ށj�A�ɐ���231�A�u����1�A�z�O��31�A�ߍ]��3�A�O�͍�5�A�R�鍑4�A�x�͍�2�A������22�A���Z��2�A������6�A������5�Ƃ������z�ƂȂ�A�ɐ����S�̋��c�ł��邱�Ƃ����������B�܂��A���Ƃ��Ɩ{�R���֓��ɂ��������Ƃ�����A�����Ȗk�ɂ����������z���邪�A�R�ԕ��ɂ͖����͑��݂��������m�݂ɂ��邱�Ƃ����M����悤�B�ɐ������i�o�ƏO���ւ̒n��ʓo��A����l���̏d������j�ɂ��ẮA���s��1�A�����Z�S32�i��20�A����3�A�Ə�2�A�͕�1�A��c�k�|�V���l1�A�Ð�1�A�˓�1�A����1�A���c1�A����1�j�A����u�S27�i���8�A�_�o3�A�ؑ�2�A���R2�A���X2�A��u����2�A����2�A�X�{��2�A�r��1�A����1�A����1�A�엯1�j�A�����|�S66�i�䎛��24�A���q7�A���c5�A���@��4�A�3�A�O��2�A��Ñ]2�A����2�A���c2�A����2�A��R1�A�����1�A�䉒1�A�R��1�A����1�A��Õ��c1�A���1�A��k1�A���啔�c1�A���ʕ�1�A�c�[�J1�A����1�A�L��1�j�A���͋ȌS20�i�k����4�A�k�����H1�A�ʊ_4�A�݉�2�A����1�A�O���s4�A�ᏼ2�A�r�c2�j�A���K���S3�i�K��3�j�A���O�d�S40�i��8�A�l�c7�A���l4�A���╔4�A������2�A�Ԗx2�A��K2�A���i2�A����2�A���K2�A�я�1�A�R�{1�A�����H1�A���q1�A�k���R�c1�j�A�������S9�i���x�c5�A�Ε��k�x�c�l2�A�x�c��F1�A���q�H1�j�A���x��S1�i�c��1�A�j�A�э��S14�i����9�A�w���c3�A�O��2�j�A���і�S1�i���c�H1�j�A���鎭�S17�i��3�A�T�R3�A�����2�A���{1�A���{1�A����{1�A����H1�A����1�A����1�A�쑺1�A���j1�A�a�c1�j�Ƃ������z�ƂȂ����B�܂�A�l���s���珼��ɂ����Ă̊C���̒n��𒆐S�Ƃ������c�ł��������Ƃ������ł���B�w�����a����L�x�ɐ�C���ɂ�����I�Ȓ���ւ̌~����̋L���������邪�A������C�ݕ��ւ̋����̐L���ƍ��킹�čl����Ɩʔ�����������Ȃ��B�܂��A���ݑ��݂��鍂�c�h�̎��@�͂�������������߁A�����ɋL�������X����ɂ��̉��ɖ����������Ă����Ƃ��l������B�Ȃ��A���̎j������́A�퍑����炾�������c��k�����X�Ɉ�g�c�𒆐S�ɂ܂Ƃ܂��Ă����p���m�F�ł���B�ߐ������A��g�c�̖{�R���͐i�s���������B�����̎��@���A�{�R�Ɍ��W���Ă������킯�ł��邪�A���̌��W�̎��ƂȂ������̂��A�����o�ƏO�����疾�炩�ɂ������B�e�a�ȗ��̗��̖����̑O��O���Ԃɂǂꂾ���̖V�傪�o�Ƃ��������o�ƏO������ƈȉ��̂悤�ɂȂ����i���ʓ��͎O���O��ɏo�Ƃ��������j�B��1���e�a11��28���i27�j�A��2���^��3��8���i2�j�A��3�����q7��4���i0�j�A��4�����7��11���i1�j�A��5�����12��18���i3�j�A��6����4��14���i1�j�A��7������6��16���i3�j�A��8���菇1��28���i2�j�A��9���茰5��24���i1�j�A��10���^�b10��22���i12�j�A��11�����^5��25���i1�j�A��12���Čb1��21���i1�j�A��13��Ꟑ^9��20���i14�j�A��14��G12��16���i�ݐ��j�A�ԊO�^�q7���S���i0�j�A��15���8��22���i4�j�B��������́A�J�R�e�a�A�����^�d�A�O�Z�̊����d��������������B�]�������Ă����A�e�a�y���A�^���d���́A�ߐ������i�K�̋V����͌��������Ȃ��B�܂�A�M�Ώۂ⎞���͐e�a�A�^�d�̊��������Ƃ��āA�n��I�ɂ͒����𒆐S�Ƃ��������m�݂Ɩk���ɕ��z���閖�������Ƃ����A���c�\���������W���鎛���Ƃ��ď�����g�c���������݂����B�܂��A�g���ȑO�Ȍ�̎��@���͗]��ς��Ȃ����ƁA��g�c�̖{�R�����i�s���ł��������Ƃ���A�g���O�̎������͂��Ȃ苇���Ȃ��̂ł������ƍl������̂ł���B
�U��g�c�����̌`���ߒ��Ɠ��ɂ̕����̈ꉼ��
�@�N��q�Y�w��y�^�@���@�̌��z�j�I�����x�i�@����w�o�ʼn�A���㎵�j�f�ڂ̎j���u�������ƕ����v�u�E�c��R��ċ��L�v�ƁA�w�^�@�j���W���x�l�A�����ɁA��㔪���́u���c�m��l��X�m�����v�u��C�������v�u�l���s�������v�A�e��������̈��c�_�Ђ̓��D�A���q�@�̓��ɂ̕����ƌ����N��A�w�@���j�x��w�����N�����x�i���Õ������s��A��Z�Z��j�����̏��j����z��g�c�����̊j�ƂȂ��e���̈ʒu�̕ϑJ�A�����̊g���Ɋւ��鉼������Ă݂��B�w�����N�����x����͋���������E�c���ƈ�g�c���̋��ڂƂ͕ʂɁA�N�v�̂�����y�n�ƔN�v��������Ȃ��y�n�̋��ڂ���g�c�����̊g���O�̋����n�ɂ��������Ƃ��킩�邪�A���̋��ڂ͕��\�O�N�̑��}���n���ɏo�����ƍl�����邽�߁A���\�ȑO�̋����n�͓����˂��g�����钼�O�̋����n�����������������Ƃ��킩��B���̌��ʁA��e���͌������̖k�������Ɍ����Ă����ƍl�����邱�Ƃ��������B�܂��A���łɏ\�̗��ɉ����Čy�������@�������̍������ړ]�v�悪���������Ƃ��������B���̌�A�����˂̋v���ːݗ��ƍ��킹�čl����ׂ��ł���Ƃ������c�搶�̎w�E�A�������Ɉړ]���X�����ӎ������Ȃ�Ό�e���͓��ʂ��邱�ƂƂȂ邾�낤���ƂƁA��g�c�̌�e���𓌖ʂɂƂ����咣�͖��ڂɊ֘A���Ă���̂ł͂Ȃ��낤���Ƃ����ʂ̕���ɂ�����w�E�A�Q�{�q�̑S�ʎ�荞�݂͓�֍s���s���قlj\�ƂȂ邾�낤���獂�����ړ]�̘b���o���̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ȃ�̍l�����o�Ă��Ă���B
�V��g�c���������ɂ������Ă̏��l�^
�@���ɏ������ɐ�������ׂ����l�^�Ƃ��āA���c�H���i��g�c�H�����j�Ȃ���̂̑��݁A�ߐ��̎ŋ������A�^�@�ɂ�����_�_���q�ɂ��Ă̑�\�I����Ƃ��Ă̈�g�c�A�_���Ђƈ�g�c��~�Ə㕪�c�Ƃ������Ɏc�鎚���Ƃ�����������������B
�����e�̌����i����E���c�j
2006�N�P��15���i���j�@��21����
�T�v
���@���e�[�}�̍Č���
���e�[�}���u�s�s�Ɛ���v�Ƃ�������Ƃ��Ă������A�S�̕Ƃ̐�������������Ƃ�A�u����v�̃C���[�W�Ƃ��ĎR�c����������邱�Ƃ���A�ēx�������Ă͂ǂ����Ƃ����ӌ������������B����̂��荇�킹�ɂ���Ă��A�e�[�}�̍Č������K�v�ƍl����ꂽ�B
����̑��́A�s�s���܂߂���Ō����鑽�ʂȗl�������邱�Ƃ�A�s�s��n��̂Ȃ��ő��Ή����邱�ƁA���邢�͍ݏ����m�⑼�n��Ƃ̂Ȃ�����l���邱�ƁA�����Ď����ʂ����s�s�̕ϑJ�����邱�Ƃ����S�ƂȂ�B�����ŁA�S�̂Ō��������Ƃ���A�u�s�s���Ȃ��v�Ƃ����Ă��o����A�S���̈ӌ�����v�����B���̂��߁A�u�s�s���Ȃ��v����e�[�}�Ƃ��ĉ^�c���Ă������ƂƂȂ����B
���@�e���e�̌����i����E�R�c�E�ɓ��E��}�E�}��E�|�c�j
�e�ʕ̓��e�ɂ��āA�S�̂̂��荇�킹���s�����B����͉���E�R�c�E�ɓ��E��}�E�}��E�|�c�̓��e�̌������s�����B
���@���w��R�[�X�̌���
�R�c���w��𒆐S�ɁA��g�c���w��̌����������s�����B��g�c���w��́A���Z�Á���g�c�R�[�X�Ƃ�������Ō������邱�ƂƂȂ����B
2005�N12��10���i���j�@��20����
����F�F�u�u�l���x��n�}�v�Ɍ��钆���O���̈ɐ�
�@�����A�u�����s�s�v�ƌĂ��T�O�̒��ɂ́A���s�E�ޗǁE���q�ȂǂƂ����������̎�̏W�Z����u����s�s�v�ƁA���ď鉺���E�`���E��O���ȂǂƌĂ�Ă����u�s�s�I�ȏ�v�i����j�̓ʂ��܂܂�Ă���A���̗��҂́A����܂œ��Ă��č������ėp����ꂽ��A���邢�͂��̈���݂̂�_���邱�ƂŖ�������Ă����悤�Ɏv���B������ɋߔN�A�������̔N�v���[�V�X�e���Ɠs翊Ԍo�ςƂ̊W���l�@���鎋��������A���̗��҂m�ɐ��������т��錤��������������B
�@�{�́A����܂œ��Ă��Ē�������̖�O���i�����O���j�Ƃ��Ę_�����邱�Ƃ̑��������R�c�̓s�s�\�����A�����O���ɑk��A����ȑ����̎�ɐ��O�{�́u����s�s�v�Ƃ��đ��������Ă݂���̎��݂ł���B�A���A�����O���ɂ�����R�c�̓s�s�\�����f���m�邱�Ƃ̂ł���j���͋ɂ߂Č����Ă���A�{�ł́A�����Ė����ɕҎ[���ꂽ�u�l���x��n�}�v���A���̂��߂̗L���Ȏj���Ƃ��Ċ��p���Ă݂��B
�@�u�l���x��n�}�v�́A�����R�N��������U�N�܂ł�112�N�Ԃ��₵�ĕҎ[���ꂽ�A�O�{�K���x��̍ł��ڍׂ��ԗ��I�Ȍn�}�ł���A�����m���錻���̌Õ����E�ËL�^�ɂ�����Z�������������̂ł��邱�Ƃ��g�Ɏw�E����Ă���B�����Ŗ{�ł́A���̌n�}�ɋL���ꂽ�x��_��Ƃ����̕c����N�㏇�ɐ������邱�ƂŁA�ނ炪�x��S�̂ǂ̕ӂ�ɋ��_���`�����Ă����̂����l�@�����B���̌��ʁA10���I����11���I�O���܂ŁA���c��ȓ��̍L�͈͂ɕ��z����ݒn�̎�I���݂ł������x����A11���I�㔼�ȍ~�A�����̌�~�i��i�n�n�����j�`���̉ߒ��ŁA�O�{���ӂɏW�Z����s�s�̎�i����̎�j�I���݂ւƁA���̐��i��ώ������Ă��邱�Ƃ�_���A���ꂱ�����A�R�c����ʓI�ȁu��O���v�Ƃ͈قȂ�s�s�\���i�U���ȂقǍL��j��L������j�I�O��Ȃ̂ł͂Ȃ����ƍl�����B
�ΐ_���e�u�K���S�E���ٌS�̒������Ё\�w��P���L�x�𒆐S�Ƃ��ā\�v
�@�w��P���L�x�͎l���s�s��x�c���ɏ��݂���P�����i��y�^�@���c�h�j�������̈���ɔ@�������̑ٓ�����݂����������ł���B������L�����̂��������d�Ƃ����l���ł���A���m�Q�N(1225)����m���Q�N(1241)�ɂ����čs�Ȃ�����P�̓��e����L����Ă���B
�@���d�́A�ɐ���F��ւ��x�X�Q�w����Ȃǂ��Ȃ�̍��͂�L���Ă����ƍl�����Ă���B���Z�n�́A���݂̈��ٌS�������t�߂Ƃ������A���ٌS���̎��Ђ��������o�ꂷ��B��Ȃ��̂�������A����i���n���A�����Ж��͌��݂̖��́j�A�u�m�i���Q�_�Ёj�A����i�v�Đ_�Ёj�A������i�n�����j�A�J�i���j�Ȃǂł���B�K���S���ł͑��x�i���x�_�Ёj���B��o�ꂷ��B
�@���x���܂߂������̎��Ђ̎��ӂɂ́A�o�˂⒆���悪�F�߂��������������A�w��P���L�x�ɓo�ꂷ�鎛�Ђ��n��̐M�̒��S�ł��������Ƃ��킩��B���ɑ��x�́A��襂ȒJ��̒n�`�̒��ő��x�_�ЂƐ_�{���𒆐S�Ƃ��āA�����̎Ζʂɒ����悪�L����A���x�_�Ђ̔w��̋u�˒����Ɍo�˂����c���ꂽ�B�ޗǎ���ɐ_�{�������c����A�ɐ��_�{�������Ĉɐ������ł����Ƃ������_�K�������Ă������x�_�Ђ́A�l�X�̐M���W�߂Ă������Ƃ͊m���ŁA�����O���̒i�K�œs�s�I�ȗv�f�������n�߂Ă����̂ł͂Ȃ����Ɛ��肵���B
�@�܂��A�w��P���L�x�ɋL�ڂ̂���ꏊ�ȊO�ɂ��A�n����l�Î������玛�@�����������Ƃ��킩��B���Ȃs�������ɂ͓��T���Ƃ����n�����c��A���ӂ���͌o�˂ƒ�����ɔ����╨���o�y���Ă���B���̑��A�o�˂ƒ����悪�ꏏ�Ɍ������Ă��鏊�ł́A���Ȃs������̌o�˒�����Q������B�w��P���L�x�ɂ͌K���ɂ��Ă̋L�q���܂������Ȃ��B�������A�ɐ���F��ւ̎Q�w�⑽���̕i�����[����ɂ������Ă͑D���g��ꂽ�ƍl�����Ă���A�����炭���̏o���`�͌K���ł������낤�B�K���̂܂��ɂ́A�k�ʏ��E���ʏ��E�@�Ԏ��Ƃ������n�������ł��c��B�u�ʏ��v�Ƃ����n�����̂��̂������O���̑m�̊������������̂ł���A�@�Ԏ��́w���ΏW�x���L�������Z���ꎞ���A�Z���Ă������ł�����B�K���͂��̂��납�炷�łɍ`���Ƃ��ċ@�\���Ă����Ǝv���A���̎��ӂɎ��@���_�݂��Ă����ƍl������B
�@���ЁE�o�ˁE�����悪���邩��Ƃ����Ĉ��Ղɂ������s�s�I�ȏ�ł������ƒf�肷�邱�Ƃ͐T�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�������R�������ɂ����Ă����͒n��̗��j��_���邽�߂̗L�p�Ȏ����ł���B����A���n��Ƃ̔�r�Ȃǂɂ���Ă���ɐ������Ă����K�v������ƍl���Ă���B�܂��A����͎��グ�邱�Ƃ��ł��Ȃ������������~�Ƃ̊W���\����������K�v������ƍl���Ă���B����̉ۑ�Ƃ������B
2005�N11��6���i���j�@��19����
���̓��e�̌����`���̂P�`
�@��P�X����́A�O�d���ŕ\��̓��e�����������Ƃ����B�\��҂ɂ��T�v�̒ƁA�S�̂̂��荇�킹��ړI�Ƃ��Ď��{�������̂ł���B
�@���e�́A�ȉ��̂Ƃ���ł���i�^�C�g���͂����������j�B
�E ���_�@�@����F�F�u�ɐ������s�s�̗��j�I�ʒu�Â��v
�E ���_�A�@���c�B���u�ɉꍑ�Ɍ�����x�z�Ƒy���Ꝅ�v
�E �`�@�R�c�Y�i�u�@���҂̌����s�s�v
�E �a�@�ɓ��T�́u�������͂���u�����s�s�v�̎��Ԃ�T��v
�E �b�@��}��u�u���ߐ��ڍs���ɐ��_�{���Ӓn��ɂ�����n��Ԍ𗬌`�ԁv
�E �c�@���с@�G�u�����s�s�R�c�̌`���Ƃ��̓����v
�E �d�@�}�䌫���u�u�s��v�n���Ɋւ��鎎�_�v
�E �e�@�|�c�����u�����s�s�Ə�s�v
�@�ȉ��A�������̉ۑ��G��Ă����B
�����e�[�}�u�i���j�s�s�Ɛ���v�Ɋւ��ā�
�@����̑��ł́A�����s�s�Ɛ���Ƃ̊W���ЂƂ̉ۑ�Ƃ��Ē��悤�Ƃ��Ă���B��L�̂����A���ڐ���Ƃ̊W�Ɋւ��̂͑��_�@�A�`�E�b�E�c�E�e�ŁA���́̕A����̑ɂɂ���u���v�̕����ɏƏ��Ă����̂ƂȂ��Ă���B��������ۂɂ́u���v�̕����̋c�_���K�v�ƂȂ邽�߁A���҂͕\���̊W�Ƃ������邪�A�S�̃e�[�}�Ƃ̊W����܂łɂ�������ᖡ���Ă����K�v������B
�܂��A���e�[�}�Ƃ��ẮA���������u���v�̕����������������̂ɕύX���邱�Ƃ��l���Ă悢�̂����m��Ȃ��B
�����e�̎����Ɋւ��ā�
�@�O�d���ł��邽�߁A�O�d���̎��e��̓��������߂Ē��鎋���Ƃ��āA�e�X�̕��e�͋ɂ߂ċ����[�����̂ɂȂ��Ă���ƍl�����A����̓��t�������Ɋy���݂ł���B�������A�O�d�����Ŋ�������c�_�ƂȂ��Ă��܂�������܂�ł���悤�Ɏv����B�f�ނ��O�d�����̎����ނƂ��Ȃ�����A�������炢���ɑ�ǓI�ȋc�_���\�Ȏ�����ł��邩���A���ꂼ��ōl���Ă����K�v�����낤�B
�����̑���
�E���P���ڂ̌��w��ɂ́A��g�c�R�[�X���V���ɒlj�����邱�ƂƂȂ����B����ɂ��ẮA�Îs���ςƓ��c�ψ����E���c�ψ��⍲�Ƃ̊ԂŒ������}���邱�ƂɂȂ��Ă���B
�E�{���̑�g�ł̂��荇�킹�́A�S���܂ł̊ԂɂR��قǍs�����ƂƂ��Ă���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���ӁE�ɓ��T�́j
2005�N10��23���i���j�@��18�����@�ɐ��n��i�R�c�E�͍�j���w�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��}�@��u
�@����́A�����s�s������Ƃ��Ă̏��̈ɐ��n�挩�w��ł���A�܂��A���N��
�����s�s������O�d���ł̌��w��̉����Ƃ����Ӗ����������˂����̂ł���
���B��v�R�[�X�͈ȉ��̒ʂ�ł���B

�@����v���w���[�g
�ߓS�ɐ��s�w�i�W���j�ˎR�c�O����Ձ˖@�Z�@�ˑ��R�����ԐՁ˒U�ߎR��n�ˎR�c��V���i�����E�ҋv���E�E�Y���j�n��i�k�o�_�@�ՁE�k�V���q��@�Ձj�ˋ،����ˊۉ���v�@�˔����s��s��n��i���������O��܁E����k�����l�n�ՁE�����݂�����v�@�Ձj�˗���v�@�Ձː{����Ёˋ{��n��i���錩�{�E�_�H�ʁE����v�@�E��Ɓj�ˊ⟺�n��i�㕔�z����@�ՁE�O���s��v���Y�@�ՁE�o�������@�Ձj�ˉ��{�n��i���ȏ����ЁE�ł̎q���E���c���j�ˉ͍�i�͍�{�ʂ�̒����݁E�����E���ՁE�͍菤�l�فj�ˍ��e��i�͍�2���ژF�[�āE���������j
�@���w�ɂ�����A�n���I�E�n��I�����Ƃ��āA�@�O�{�����O���R�c�i�͍�܁j�����ł������茩�w����Γk���ł͂S�E�T���Ԃ��炢�͂䂤�ɂ������Ă��܂��قNj���Ȓ����O���ł��邱�ƇA�R�c�ɂ����ċ����̏ꏊ�̂܂܌�������ɐ���t�̓`���I�ȓ@��͂Q�Ƃ����ł���A���̑��͓@��Ւn���唼�ł��邪�A�����s��̖��������O�⒆����͍�̒����݂ȂǕ����I�ɂ͍]�˂��珺�a�̓`���I�ȉƉ��͎U�݂��Ă��邱�ƇB�]���̎w�E�ʂ�A������������́u�� �E�x�v�ł��鐴�삪���Ƃ��Ă̎R�c����ԓI�ɋK�����Ă��邱�ƇC�����̓��i�X���␢�Áj���悭�c���Ă��邱�Ɓ@�Ȃǂ������ł����B �E�x�v�ł��鐴�삪���Ƃ��Ă̎R�c����ԓI�ɋK�����Ă��邱�ƇC�����̓��i�X���␢�Áj���悭�c���Ă��邱�Ɓ@�Ȃǂ������ł����B
�@���̂��߁A���ł̌��w��ɂ����ẮA��L�̓����܂������悢���w���[�g������i���ɒ��ԏ�Ƌx�e�ꏊ�̖��j���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��킩�����B�܂��A���̂悤�ȓ�������藝�����邽�߂ɂ������j�w�I�Ȍ����ۑ�Ƃ��āA����@���s�s�ł��钆����������̎R�c�̓s�s�̎��Ԃ������Ɩ��m�ɂ���K�v������ƍl������B
2005�N�X��19���i�j�@��17����
�S���V���|�W�E���w�����q�Ƃ̏����x�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ɓ��T��
�@���̃V���|�́A�����s�s������2005���s���Ɠ����̂X���R�E�S���ɊJ�Â���A�M�҂͕҂Ƃ��ĎQ�������B���e�́A�ȉ��̒ʂ�i�h�̗��j�B
�X���R���i�y�j
�u�L�O�u���F�����̐��^�Ɠ�����v��ݏ��v�A�u���ˌn�v���V�ǗS�A�u�튊�E�����v���쐰�v�A�u�{�b��n�v����ɏt�A�u����v�X���N�Y�A�u����炯�v����֎j�A�u�y���ϐ���v�ɓ��T�́A�u�����{�v�ё���
�X���S���i���j
�u��F�E��F�n�v���c�V�H�A�u���C�v��ؐ��M�A�u�E���v���{�v�a�A�u���˓��v��؍N�V�A�u�f�Փ����v�R�{�M�v�A���p�l�����_���i��F�Ċ_�E�v�E��쐰��
�@����̃V���|�ɍ��킹�č쐬���ꂽ�����W��800�y�[�W���z���A�S���e�n�̓y��ҔN���f�ڂ��ꂽ�B���̋ߗׂł́A���ˁE�튊�E�M�y�Ƃ������ҔN�\������A�ŐV���ʂ����荞�܂�Ă���A�d��ł���B
�@�V���|�̓��e�́A�Z�p�_�����Ɋւ���c�_�����S�ł������B���V���������u���Y���j�b�g�̈ړ��v���A���ˌn�q�ȊO�ł������邩�ۂ��Ƃ������ϓ_�́A����d�������ƍl������B�܂��A���V���̂ق��M�҂��y��̏ڍׂȊώ@����S�Ă��n�܂邱�Ƃ����������B�ۑ�Ƃ��ẮA���e�̖L�x���ɑ��Ĕ��\���Ԃ����ꂼ��Q�T���ƒZ���������ƁA�����W�̐}�ʂ����Ɍ��Â炢�i�Ƃ��Ɏʐ^�j�ł��������Ɓi���Ȃ݂ɁA����͂o�c�e�t�@�C�����玆�Ă��̃_�C���N�g����j�Ȃǂł���B
�@���Y�Ɋւ���c�_�́A���ʂɊւ�����ɂ��傫���W����B����̓����Ƃ��Ă͗��ʂɊւ��錟�����i�߂��邪�A����̂悤�ȃV���|���J�Â���邩�ǂ����͖���ł���B
�@���ɂ͂R�Q�O�l���z����l���W�܂�A�y��ҔN�Ɋւ���S�̍������킩��B���s���ƍ��킹��A���̓����Ȃ�̌����҂������Ɋւ���V���|�ւƏW�������ƂɂȂ�B����炪���������Ɋւ���S�̍����̈Ӗ����[���ɍl�����Ă����K�v������B
�u�����s�s������s���v�@�@�@�@�@�@�|�c����
����9���R�E�S���ɒ����s�s������s���ԉ���w�ŊJ�Â��ꂽ�B
���̊�{���O�́A
�@�������s�����̂���܂ł����A���ꂩ���W�]����@
�A�������s��������S���̒����s�s�����ɔ��M����
�B���s�𑊑Ή�����
�C���s�����l���Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���s�����[���l���邱�ƂŒ����s�s�̖{���𖾂炩�ɂ���
�D���s�ŗL�̖��ł͂Ȃ��A���s��_���Ȃ���A���ꂪ���̓s�s���l�����ł��Q�l�ɂȂ�e�[�}�ݒ���s��
��5�_�ł���B
���̕��j�̂��ƁA
�i�P�j�m�؍G�u���{�̒��̋��s�\���́E�o�ρA�n��Ɓu��s�v�\�v
�i�Q�j�S�����P�u�������s�\�s�s��̗l���Ɛ��Y�E���ʁE����v
�i�R�j������u�����O���̌��͂Ɠs�s�\�@�䏊�E�����E�Z�g���\�v
�i�S�j�����N�v�u�`���ꂽ���s�\�㐙�{�������O�}�����̎����a���߂����ā\�v
�i�T�j���c���Ɓu�G�g���ʂ����Ȃ������Ԍ��\���������̐A�����߂����ā\�v
�i�U�j��p���T�u�������s�̒n�`���ω��v
�i�V�j�R�{��a�u�������s�̊X�H�ƒ����v
�i�W�j�͓����F�u�����̍�Ɠs�s��ԁ\�_����_�`�n��ƌ䗷����f�ނɁ\
�i�X�j�������F�u�����E���O�̏�قƏW���\�s�s�ߍx�_�v
�i10�j�R�c�M�a�u�����Ƙ_�_�\���{�s�s�j�����ɂ�����u�K�w���v�̒\�v
�̂P�O�l�ɂ�锭�\���������B
�m�؎�������܂ł̋��s�����̗���Ƃ��̖��_����A���̌�S�������畟���������ꂼ��̐�啪�삩��A�ŐV�̋��s�����ɂ��Ă̘_�l�����\���ꂽ�B����������ĎR�c���������Ƙ_�_�������s���A���c���s���Ƃ����`���ł���B
�X�̔��\�́A�������̐퍑���̎����a�E�Ԃ̌䏊�Ɋւ������N�A������E�������̋��s�Ƃ�����ƕ��ƁE��s�Ƃ̊W���͂��߁A���Ɋ����x�̍������̂ł������B
�^�c�Ɋւ��Ă��X���[�Y���X�}�[�g�ɍs���A���̖ʂł��w�Ԃׂ��Ƃ��낪�������ł������B
2005�N�W��30���i�j�@��16��ψ���
�P�@�Q�O�O�U�N�O�d���ɂ���
�E �Q�O�O�U�N�x�e�[�}�@�i���j�u�s�s�Ɛ���v
�E�@���w�j�i��P�Q��ψ�������e�ɂ��Ȃ��j
�E
�n��I�ɂ́A�ɐ��E�u���E�ɉ�E�I�ɂ���ȑf�ނƂ���B
�E �ɐ��p���݈�͖��Â������Ȓn��ł���A���̑��݂��ӎ����ĒNj�����B
�E
���̈���ŁA�u�C�̘H�v�Ƒo�����Ȃ��u���̘H�v���d�������v�l��ڎw���B
�E
���Ȃ����ߓ_�Ƃ��Ă̒n��I�������d�����A���̗��j�I�w�i��Nj�����B
�E �ɐ��_�{���͂��߂Ƃ����@���I�v�n�Ƃ��Ă̂�������ӎ�����B
�E
�j�̂Ȃ��ł��d�v�ȗv�f�ł���A�ɐ��_�{�����n��I�E�o�ϓI�ȉe���͂��ӎ�����B
�E
��L�ɂ��A���s�i�����j�⊙�q�i�����j�𒆐S�Ƃ����j�𑊑Ή�����v�l��Nj�����B
�E�҂Ɠ��e
�Q�@���̓��e
���@����
�����G�Q�O�O�U�N�X���Q�E�R���i�y�E���j
�ꏊ�F����i�Éw�ߗׁj
�^�c���@
��P���ځi9/2�j�͏I�����w��A��Q����(9/3)�Ɍ�����B
�P���ځi�X���Q���j���w��
�{���j�����ُW��
�@
�����������W�u�i���j�k�����Ƃ��̎���v�̉���ƌ��w
�E����i�|�c���ɓ��j���G�{���j�����ٍu��
�@�E�W�����w
�A�@���w��
�E�`�R�[�X�i�F���R�c���ʁj
�E�a�R�[�X�i���C�j�@
�A ���e��
�E��ꖢ��i�Éw���Ӂj
�Q���ځi�X���R���j�����E�V���|�W�E��
�W�F�R�O�`�@��t
�X�F�O�O�`�X�F�O�T�@���A�E��|����
�X�F�O�T�`�P�O�F�O�O�@��E���_�@�@����F�F���i�����O���j�E���c�B�����i��������j
�P�O�F�O�O�`�P�O�F�S�O�@�`�i�M�ƕz���j�R�c�Y�i��
�@�@�x�e
�P�O�F�T�O�`�P�P�F�R�O�@�a�i�������͂ƒn��j�ɓ��T�̎�
�P�P�F�R�O�`�P�Q�F�P�O�@�b�i�R�c�E�喩�Ƌ��Z�j��}��u��
�@�@���x�݁E�}��������
�P�R�F�Q�O�`�P�S�F�O�O�@�c�i�s�s�Ƃ��̏�j���яG��
�P�S�F�O�O�`�P�S�F�S�O�@�d�i�s��j�}�䌫����
�P�S�F�S�O�`�P�T�F�Q�O�@�e�i��ٗ��n�j�|�c������
�@�@�x�e
�P�T�F�R�O�`�P�U�F�R�O�@���c�@�i��G�d���NjI���E�T�R����
|
|
2005�N�V��23���i�y�j�@��15����
���J�L�u��Տo�y�̑K�݁v
�@����̔��\�ł́A���@�������ɏo�y����K�݁i�⎸�K�j���A�ǂ�Ȏ�ނ̂��̂��ǂ�Ȉ�Ղ���o�y����̂��A���̌X����T��ׂ������W���������̂ł���B�]���̏o�y�K�݂̌����͔��~�K�⒆����o�y�̘Z���K�Ɋւ����̂����S�ł������B�������A�����̑K�݂ɂ͉��炩�̎w���A�Ӗ��t��������\��������A���@�������ɕ�ܑw������o�y����K�݂̕�����蓖���̗��ʂ������̂ł͂Ȃ����Ƃ̎w�E������A����͂���ɑ����ďW���������B�����ނˁA�k�v�K�E���K�Ƒ傫���Q�ɂ킯�A���ꂪ�ǂ��̈�Ղ���o�y���Ă���̂������Ă��������A��������L���Ă����B
�@�P�C����Ȃ�̒����W���ł͂���Ȃ�ɑK�݂��o�y���Ă���A�P���Ƃ����̂͂قƂ�ǖ����������o�y���邱�ƁA�Q�C�k�v�K�͒����S�ʂ�ʂ��ďo�y���邪�A���K�͈��ʂ��A������Ă���ƍl������P�T���I�ȍ~�ɂȂ��Ă����~�K�E������������ƈ�ʏW������̏o�y�͂��܂茩���Ȃ����ƁA�i�t�ɔ��~�K�⒆����ɂ͉i�y�ʕ���������X��������j�A�R�C���K���o�y�����Ղ͈��Z�Â�k�����ِՂȂǓ���̈�Ղł���\�������邱�ƁA�����l����ꂽ�B����̉ۑ�Ƃ��ẮA�K����ׂ������邱�Ƃɂ��A�g�p���@�◬�ʂɈႢ������̂������̂��A���~�K��Z���K�ȂǂŎg�p�����K�݂Ƃ̈Ⴂ������̂��A�o�y�����ՂƂ��Ȃ���ՂɈႢ������̂��ȂǁA���ׂ邱�Ƃ͑����B
�������g�u�L���_�{���l���̎��v
�@����A���\�����Ē������u�L���_�{���l���v�́A�����l�N�̐_�_�����ɍڂ��Ă�����̂ŁA�u�����ԕ����蕣�B����{�R�B������������R�����B�k���{�́v�Ə�����Ă�����̂��A����܂łɁA��ސ����A�吼����A�@���R���������A���ۂ̒n��T���āA�l�X�ɔ�肵�ė������̂ł��B
�@�����ł́A�n���Ɉ₳��Ă��鎚�n���⎑�����g���A��蕣���R�c�ƉF���̋��E�n���J�ƌĂꂽ�n�A�R���������݂̋{��i�h���f�j�A�{�͂�k�{��̗���Ă����ᑠ���ߕӂɐݒ肵�܂����B���̐ݒ�ł́A���ꂼ��̋����O�{���a���瓙�����A�܂��A���l�������`�ɂȂ�A�ߎl���ƌ`���������ƂɂȂ�܂��B
���c�B���u�t���̓W�J�v
�@�U���E������_�Ƃ��Ă̋@�\���ʂ����v�ǂł���t����A�{�鋉��s�̎��͂ɂ����Z���Ԃɑ����\�z���ēG�ΐ��͂��Ǘ�������Ƃ�����@�́A�퍑��������D�L���ɂ����đS���ƂȂ����B
�@�D�L���̐푈�́A�ꎞ�I�ȏ��s����ɂ���̂ł͂Ȃ��A��̒n���̍��ɕғ����A����ɂ͓G�ΐ��͂̑��̍����~�߂�E�C��ւƎ��I�ɕω������B�t��Q��L���Ɋ��p������p�́A����ɏƉ�������̂ł������B
�@�M�����͂��߂Ƃ���V���l�B�ɂ́A�t���𐋍s���鎑�{�ƋZ�p���~�ς���Ă����B�t���ɂ́A�G����͂���t��Q���z�u����A�������Ȃ��o���P�[�h�Ƃ��ċt�Ζ�y�ۂ���������A�x���������Ƃ��������B���������Đ��U�߂��A���̈�`�Ԃɑ�����B
�@�{�ł́A�t����퍑���̍��S���ڐ�ɑ����푈�j�ɂ������i�K�Ƃ��Ĉʒu�Â��A���̏����ɂ��ĊT�ς��邱�Ƃ����݂��B
2005�N�U��18���i�y�j�@��14����
�g����ƕ����Ɛ����������̒���
�����������ɂ���
�@�T�R�s�֒������̐������ɓ`��镶���Q�̂����A�{������̑ΏۂƂȂ钆���̎j���ɂ��āA�����҂̂��z���ɂ��q�������Ē������Ƃ��ł����B
�@�����肠�����j���́w�ݏ��R�i���T����@�m�O���x�E�w�c���N���s�����K���@�ݏ��R�i���T���K���ĔV�{�咠�x�E�w�i�\�ܔN�\�����@�K���[���x�̂R���̒������@�Ɋւ��j���Ɗ֖��S�ւ̏��ł���B
�w�ݏ��R�i���T����@�m�O���x�E�w�ݏ��R�i���T���K���ĔV�{�咠�x�͊֒���ɏ��݂����Ƃ����i���T���Ɋւ��鎑���ŁA�w��@�m�O���x�͌��W���Ƃ��ĉi�����N����V���S�N�܂ł̜�@�m152���̖��O�Ɣ[�߂��z(������200��)���L����Ă���B�i���T���𒆐S�ɍs��ꂽ�u�O�̖���Ǝv���邪�A�֎��튯�̏��쎁���ώ��A�t�ᎁ�̓a���w��s��܃t�N������E��H�Ȃǂ̏��E�l��������B�܂��A��@�m�̖��O����͗鎭�쒆����ɕ��z���Ă��邱�Ƃ��킩��B����A�w�K���ĔV�{�咠�x���K���Ă̔[�z�Ǝ{�傪�L���ꂽ���̂ŁA75���̖@�����L����Ă���B�M�Ղ��烊�A���^�C���ŏ����������Ă������l�q���M����B�����ł́w��@�m�O���x�Ɍ����Ȃ������֎��₻�̈ꑰ���͂��߁A�a���w�⏗���A�����E�_��A���E�l�A�̎�튯�ȂǕ��L���K�w��������B�@���͑����̊K�w�ɑΉ����A���l�̎�W�͑勏�m���T���(��)�A���q�E�����A�a���͑T���(��)�A����ȊO�͑T��(��)�ƂȂ��Ă���B�܂��A���̎{�咠�Ɍ����閼�O���鎭�쒆����ɕ��z���Ă���B�Ȃ��w��@�m�O���x�Ɍ�����u����a�����E�L���v�i�[���j�A�w�K���ĔV�{�咠�x�Ɍ�����u����V������v�͌�������ɗR�����閼�̂Ǝv���A�����̋��{���x����m���ŋ����[���B
�@�w�i�\�ܔN�\�����@�K���[���x�́E�i�\�ܔN�ɍ쐬���ꂽ�K���Ă�[�߂邽�߂̔N�v���̗ނŁA�u���v�͐��������w���ƍl������B���@�����̑g�D�Ǝv�����Z���A�K�����Ȃǂɂ��ꂼ���K���āE����[�߂Ă���B�X�̍��ڂ͔N�v�̔[���z�Ƃ��̓���A�c�n�̏��ݒn(��)�A��l���L�ڂ������̂Ō����N�v���L�ڂ���鍀�ڂ��݂��邱�Ƃ���A���n�q���̗ނ̉\�����w�E���ꂽ�B�c�n�̏��ݒn�̔����͌��݂̎����ƈ�v���A��l�̕��z�͂�͂�鎭�쒆����ɕ��z����B�܂��A�����N�v�͕�ώ���t�ᎁ�ȂNJ֎��튯�����悵�Ă���A���̎傪�{�N�v�n�̌����N�v�����悵�Ă����l�q���M����B
�@�ȏ�Љ���R���̒������@�Ɋւ��j������A�i���T���␐�������@����}��Ƃ��ė鎭�쒆����̍ݒn�̑����ɉe���͂��y�ڂ��Ă������Ƃ��M���A��������̓��n��̍ݒn�̗l�q��m���Ō������Ȃ����̂ł���B�i�}�䌫���j
�Q�O�O�T�N5��14���@��P3����
�d���NjI�u�퍑�E�D�L���̎l���s��̍\���v
�@�{�́A���\�R�N(1594)�̎l���s�ꌟ�n���̕��͂���퍑�E�D�L���̎l���s����E�l�@�������̂ł���B���\���n���ɂ݂��鏬�������A���a�T�N�i1768�j�u�l���s���G�}�v�ɂ݂���n���Ƃ̑ΏƂ��A�����N��(1611�`1673)�̎l���s���G�}�ɒn�������Ƃ����B���̌��ʁA�L�b���̎l���s���͍]�ˎ���̎l���s����Ƃقړ����ł���A���C�������𒆐S�ɔ��W���A�����E�k�����J������Ă��������Ƃ��킩�����B���~�n�͓��C����́u�k���v�E�u���v�A����ɓ��C���Ɍ���铌���̓��H�Ɉʒu���闼�[�́u���m�o���v�u�͂ܒ��v�ɏW�����Ă���A����ɍ]�ˎ���̓쒬���ӂƐ��肳���u���v�ɂ͉��~�n���ő吔���݂��Ă����B���̂��Ƃɂ��A���n���ɂ́u���v�ƔF�����ꂽ�u�k���v�u���v�u�͂ܒ��v�ƁA�u���v�Ƃ͔F������Ȃ����~�n�W�Z�n��́u���m�o���v�u���v������A�O�҂͌��n�ȑO����́A�܂�퍑�����瑶�݂��钬�ŁA��҂͓���ƍN���̌�ȍ~�`�����ꂽ���Ɛ��肵���B���������āA�l���s�͐퍑���ɂ͓��C����̖k�����ӂƖ��́u�͂ܒ��v����Ȃ�A�L�b���ɂ͐����Ɠ��C���암�ɉ��~�n�W�Z�n�悪�L�����Ă������̂ƍl�����B
�ȏ�A�l���s��̍\�����l�@�������A�l���s�͏]���l������悤�ȍ]�ˎ���̌\�O���n�ݎ��ɒ����o���Ă����̂ł͂Ȃ��A���łɐ퍑�E�D�L���ɂ��Ȃ�̓s�s��Ԃ��������Ă����Ƃ�����B
�Q�O�O�T�N�S���X���@��P�Q����
��P�Q����́A2005�N�x�̉�^�c��2006�N���Ɋւ��Ă̑ō������s���܂����B
�����̉^�c��
���P��������ɁA����I�Ɏ��{���邱�ƂƂ��Ă��܂��B���̏��́A�g�o�́uSchedule�v�𐏎��������������B�Ȃ��A�Q���́u�v���V���|�v���J�Â���\��ł��B
��2006�N���̎w�j�ɂ��ā�
�S�̂̎w�j�Ƃ��āA���̂悤�Ȋϓ_���o����܂����B
�E�n��I�ɂ͈ɐ��E�u���E�ɉ�E�I�ɂ���ȑf�ނƂ��Ĉ������ƁB
�E�ɐ��p���ݒn��̖��Â������Ȓn��ł���A���Â̑��݂͈ӎ����ĒNj����邱�ƁB
�E���̈���ŁA�u�C�̓��v�Ƒo�����Ȃ��u���̓��v���d�������v�l��ڎw�����ƁB
�E���Ȃ����ߓ_�Ƃ��Ă̒n��I�������d�����āA���̔w�i��Nj����邱�ƁB
�E�ɐ��_�{�𒆐S�Ƃ����@���I�ȗv�n�Ƃ��Ă̑��݂��ӎ����邱�ƁB
�E�n�挠��Ƃ��Ă̈ɐ��_�{�����S�����������m���ݒn��𒆐S�Ƃ����ɐ��p���ݕ��̗��j�I�E�n���I�ȉe���͂͗j�̂Ȃ��ł��d�v�ł��邱�ƁB
�E���̂悤�ȓ�������A���s�i�����j�⊙�q�i�����j�𒆐S�Ƃ����j�𑊑Ή�����v�l���ӎ����邱�ƁB
���������̍쐬�ɂ��ā�
������ɍ��킹�āA���s�ψ���ɂ�錤�������쐬���܂��B�f�ڐ�́wMiehistory�x�i�O�d���j����������j�Ƃ��A���W���Ƃ��āo�O�d�̒����p��ҏW���邱�ƂƂ��܂����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�ȏ�A���Ӂ@�ɓ��T�́j
2005�N�R��19���@��11����
�e�[�}�u�u���b�N�`���~�n�Q�̌����v
���T�v��
�@
�@����̗��́A�ߔN�̔��@�����Ŋm�F����̑����u�u���b�N�`���~�n�Q�v�̎��ጟ���𒆐S�ɁA��������Ŏ��{�����B���e�́A�u�u���b�N�`���~�n�Q�����̌���v�i�ɓ��T�́j�A�u����s���È�ՁA���сE������Ղ̔��@�������ʁv�i�R���R�I�q�j�A�u�O�d���K���s�u�m��Y��Ղ̒������ʁv�i���䖤�I�q�j�ł���B
�@�ɓ��́A�����W�������̌���Ɖۑ���������邽�߂ɁA���ݍł��܂Ƃ܂����������ʂƂ����鍲�v�ԋM�m���ɂ�錤�����p��f�ނɁA�����W�������Ɋւ������N���s�����B�R�����͏��È�Ղƒ��сE������Ղ̒������ʂ��A���䎁�͎u�m��Y��Ղ̒������ʂ��Љ�A���ꂼ��̈�ՂŊώ@�����l�X�ȓ����������B
�@����̌�ɁA��������s�����B�����j������M�����Վ��ӂ̏����A�@���I�v�f�̏d�v���A���Ƃ̊W�A���~�n�̎��Ӗ��A��و�ՂƂ̔�r�����ȂǁA�����W����Ղ����������ł̏d�v���ڂ��A������Ղɑ����čĊm�F���邱�Ƃ��ł����B�ł��d�v�Ȃ̂́A���@�����Ŋm�F�����W����Ղ������̋敪�ɉ������߂邱�Ƃ����܂茚�ݓI�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��ĔF�����邱�Ƃ��ł������Ƃł��낤�B���ꂼ��̏W����Ղ�]������ɍۂ��ẮA��ɕ��ނ�����̂ł͂Ȃ��A�l�X�ȏ��Ȃ��猟����[�߂Ă����K�v�����邱�Ƃ����ʔF���Ƃ��Ď����Ƃ��ł����Ǝv����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�ɓ��T�́j
�u�u���b�N�`���~�n�Q�����̌���v�i�ɓ��T�́j
�@�����̏W����ՂɊւ��錤���̂Ȃ��ŁA���v�ԋM�m�������ꂽ���ވāi���v�ԁu���@���ꂽ�����̑��ƒ��v�w��g�u�����{�ʎj�x��X���@1994�N�j��w�}���E���{�̒�����Ձx�i���쐳�q�ҁA������w�o�ʼn�@2001�N�j�ł̋L�ڕ��@���Љ�邱�ƂŁA������̑f�ނ�����B�����W����Ղ̕��ނ̂Ȃ��Łu���v��u���v�Ƃ������敪���̂��̂��K�����ǂ����i�\���ǂ����j�A�\�ł���A�ǂ̂悤�Ȏ��p���猩�邱�Ƃ��ł���̂ł��낤���B�����̋敪�ɓ��Ă͂߂邱�Ƃ��d�v�Ȃ̂ł͂Ȃ��A���̈�Ղ������ɓǂ݉����Ă����̂����l����f�ނƂ��ĕ��ނ��s���Ă����K�v������B���@��������̌������̂��̂���A������l���Ă������Ƃ��d�v�ł��낤�B
���䖤�I�q�u�K���s�u�m��Y��Ղ̒������ʁv
�@��������u�m��Y��Ղ́A�ꕶ����E�Ñ�`�����܂ł̕�����Ղł���B
��Ղ̈ʒu�@�u�m��Y��Ղ́A�k�����ِ삪����A����K���Ƌߍ]�����Ԕ����X�����ʂ��Ă����ʂ̗v���ł���B�����X���Ɋւ��ẮA�ߐ��́A�Ԗ쒬�c�����璩���쉈���ɉ���A�x�c�t�߂œ��C���ɍ������邪�A�����͑�����~�˂�����ِ쉈���ɉ���A��䋴����K���֔�����Ƃ����B�܂��A�u�m��Y��Ղ̎��ӂ́A���Q�_�Ђ�i�`�j���i�����~�Ղ�u�m��E���c�邪���݂���B
�@�����̒n�А}�ɂ��ƁA����Ղ͎��\�����A��������{�A���瓰�Ƃ�����������A�t�߂ɑ傫�Ȏ����������Ƃ��`�����Ă���ƂƂ��ɁA�߂��̘@�h���̎R���͌i���R�Ə̂��Ă���B
��\�̊T�v�@�����O���́A�����̍a�ƂƂ��Ɍ���Ɍ����鉮�~�n����悷��a����s���Č@�킳��Ă���\��������B�����āA��˂�y�B�A�擙����ՑS�̂Ɍ��o���Ă���B��Ȉ╨�́A�n���y��A�R���o�A�y�t��M�A��ɐ��n�y�t��瓙�ł���B
�@������������������A�����̍a�A��ˁA�y�B�������o���Ă���B�a�́A�u�m�t�߂̕\�w�𗢕���18�`20���Ɠ��������ł���A���~�n���͂ލa���`�����Ă���B�����ča�Ԃ̋����͂��悻28�`36���͈̔͂ŁA�S���~�n������B��ȏo�y�╨�́A�n���y��A�V�ڒ��q�E�������̐��˔��Z���i�A�y�t��M�A���k���n�y�t��H�����ł���B
���~�n�̌����@�S�̉��~�n�ɂ��āA�������������Ȃ������������邽�߂ɇ@�f�Փ����̕��z�A�����̍��̕��z�B�u���v�Ɋւ���╨�̕��z�C�n���y��̕��z�����݂��B�@����́A�S�̂ɏo�y����������̂̋��S�ɏW������B�A����́A���Q���`������a����̏o�y�������A���Q�ŋ��n�̉�̓��̍�Ƃ��s���Ă����B�B����́A�����`������a����̏o�y���ڗ��B�C����́A���Q�������Ƃ����Ȃ��B�Ƃ������ʂA���Q�Ɋւ��ẮA���̋��ƈقȂ�l�����M�����B
�����Ɖۑ�@�@��Ղ̎��ӂɂ��āA���ӂ̊�����j�I�w�i�i���i���ⓡ�����d�̂悤�ɓ��n��ɂ䂩��̂���l���j���ɂ��ėl�X�Ȃ������A���ׂĂ����K�v������B
�A���ÁE���ђ�����ՂƂ̌�������A���ʂ���v�f�i�o�y�╨���j�������A�W����Ղ��������Ă����v�f�̒��o�����ɓ���B
�B�u�m��Y��Ղ́A�Ñ�`�����܂Ōp�����Ĉ╨�������邽�߁A����X�ɏڍׂȈ╨�E��\�̎������肪�K�v�ł���B
��10����@2005�N�Q��12���i�y�j
�u�k�����ِՑ�12�����@��������̌��w�v
�u�k�����ِՂق��o�y�y��̌�����`���s�n�y�t��𒆐S�Ɂ`�v

�@����̗��́A�k�����ِՑ�12�����@��������i�������㑽�C�A�k���_�Ћ����j�̌��w�ƁA�o�y�╨�̌�����𒆐S�ɍs�����B���n���w�́A���@�����S���̐Ε����l�E���яr�V�̗����ɂ��������f�����B
�@��P�Q��������ِ͊Ցz��n�̂قڒ��S�����ɂ�����B��N�x���{���ꂽ��P�P��������̓�ɐڂ��Đݒ肳�ꂽ������ł���B��P�P��������ł́A�ِՂł͂��߂Ė��m�ȑb�Ό����i�O�����n�ʏ�j���m�F����Ă���B���̓�̏�c������ƂƂ��ɁA�ِՒ��S���̗l�q��c�����邱�Ƃ��ړI�Ƃ��ꂽ�����ł���B
�@�����n�́A�ɐ��p�䕗�ŕ��������y�����R���߂��͐ς��Ă����B���̉��ɂ́A��Q������Ԃ��Ȃ��܂ő��݂��Ă������w�Z�Z�ɐՂ�����A����ɂ��h��������A��\�ʂ͂��܂���肵�Ă��Ȃ��ł������B�������A��11�������悩�瑱���b�Ό��������݂��Ă��邱�Ƃ�A�I�����s�b�g�Ȃǂ��������B�����̈�\�́A�������16���I��ȍ~�ƍl��������̂ŁA�k�����ِՂ́u������n�ʁv�Ƃ����i�K�ɁA�Q�����ȏ�̌����Q�����݂�����̂ƍl������B�܂��A�h���y��s�b�g�Ȃǂ̒f�ʂɌ��ꂽ���n�w�̏���́A�u�O�����n�ʁv�̉��ɂ���\�ʂ����݂��Ă���\���������A�u�v���O���ʁv�����݂�����̂ƍl������B�Ȃ��A���w������\�͑�����������n�ʂɑ���������̂ŁA�O�����n�ʂ̏́A����p�����钲���Ŗ��m�ɂȂ낤�B
�@���n���w��A�����������������������ɉ����ړ����A�o�y�╨�̌��w�ƌ������s�����B�╨�́A�k�����ِՂ̂ق��A������O������ՁA�l���s�s�Ԗx��ՁE�ēc��ՁA�֒��i���T�R�s�j�����s���ՁA�T�R�s���ՁE�T�R��ՁA�Îs���Z�È�ՌQ�A���s�i���ɉ�s�j�������ِՂȂǂ̏o�y�������A�l���s�s���ρE�T�R�s���ρE�O�d�������������Z���^�[�̋��͂̂��Ǝ��Q���A�������s�����B���������́A���15���I�㔼����16���I��ɂ����Ă̋��s�n�y�t��𒆐S�Ƃ������̂ł���B���s�n�y�t��́A�p������f�n����ՒP�ʂňقȂ���̂́A��@�I�ɂ͔��ɗގ����Ă���A�Ƃ��ɕēc��ՂƖk�����ِՂ̎����͋ɂ߂ėގ��������̂ł���B�܂��A�Ԗx��Ղő�M���o�y���Ă��邱�Ƃ͑�ϋ����[���B����ɁA��r�����Ƃ��Ď��Q�����e�n�̒��k���n�̎M�ނ́A��Ֆ��ł̈Ⴂ������悤�ŁA��ɐ��n�Ƃ͍ۂ������Ⴂ�������Ă���B���̂悤�ȁA�y��̌`�Ԃ������n��̈Ⴂ�Ƃ͉��ɋN������̂ł��낤���B�y�����������Ă̌�����́A���ɗL�Ӌ`�ł���A������p���I�ɊJ�Â��Ă����Ӗ������낤�B
��Ռ��w�Ǝ��������ɂ́A���������ς̐Ε����E���ю��ɑ�ς����b�ɂȂ�܂����B���肪�Ƃ��������܂����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���ӁE�ɓ��T�́j
��X�����@2005�N�P��29���i�y�j
���яr�V�u��������ɂ�����ɉ�̒n��\���ƒ뉀�v
�ɉ�n���ł́A�܂�ɕs��`�ő傫�ȓy�B�����o����邱�Ƃ�����B���̓y�B�́A���̖��y���S����ттĂ��邱�Ƃ���u�����y�B�v�u������\�v�Ƃ����]��������Ă���B�����̑����͒�����ق̔��@�����Ō��o����Ă���A�����̂����ꕔ�͕����ɂĒr�ł���\���͎w�E����Ă������̂̏ڍׂɌ������Ă�����̂͂Ȃ������B�����ō���́u�����y�B�v�u������\�v�̗���V�����i���C�J�ِՁA�@�Ԏ��Ր���n��ՁA�������ِՁA�e�i����ՁA���c���ِՁA�_�m�؊ِՁA��Y��Ձj�A�����̋��ʓ_��y�B�����̏�ԁA���~���ł̔z�u�ɒ��ڂ��A���̂S�_���������邱�Ƃ��w�E�����B
�@(a)�������߂���_
�@(b)�Ӑ}�I�ɐ�z�u����K�v������_
�@(c)�剮���炱���̓y�B���Ղ߂鋗���ɂ���_
�@(d)�����������ɂ�莋�o�I�ɎՒf�������̂�����_
�@�P�Ȃ�ꓙ�̎{�݂ł͂��̂悤�ȏ͕s�v�ł���B�܂�(d)�̓_����͉��~���̓����Ԃ̈ӎ��i������u�n���v�u�P�v�̈ӎ��j������������B���̂悤�ȓ_����ɉ�́u�����y�B�v�u������\�v�����r��\�̉\�������邱�Ƃ��w�E�����B
�@�܂������̈ɉ�Ō������\�ƑS���Ō����钆������̉��r��\�Ɣ�r�B�ɉ�n���̏ꍇ�͒����K�͂̏�ق≮�~�ɂ܂ʼn��r������Ă���B���r�͂�����x�̌��͂̑��݂��M������̂ŁA�u�y���v�Ȃǂƕ\������钆������̈ɉꍑ�̏����ꌠ�͂̕s�݂�\���Ă�����̂ł͂Ȃ����A�ƍl�����B
�@���\��ɂ͈ȉ��̖��_���w�E���ꂽ�B
�@�@�P�@�����I�Ȍ������܂���������Ă��Ȃ��̂ŁA�ă`�F�b�N����K�v�����邱�ƁB
�@�@�Q�@�P�Ȃ鐅���Ƃ̈Ⴂ�ɂ��āB
�@ �R�@�ɐ����̕��암�Ō������`�y�B�Ƃ̈Ⴂ�͂��邩�B�܂������̓����I�ȓy�B�Ƃ���r����K�v������̂ł͂Ȃ����B
�@�@�S�@�ɉ�̗�ł����Ɍ������ׂ��Ⴊ����A����Ƀf�[�^���W�ߌ�������K�v�����邱�ƁB
�@�@�T�@�뉀�j�̗���̒��ňʒu�t��������K�v�����邱�ƁB
�@�@�U�@�Y����\�̋ߗׂɓ����I�Ȉ╨�͏o�y���Ă��Ȃ����B
�@�����I�Ȍ����ɂ��Ă͍���̑傫�ȉۑ�ł���B�ЂƂ����ɒ�������ƌ����Ă��P�T���I��ƂP�U���I��͎Љ�\�����̓_�ő傫�ȈႢ������A���r��\�̔w�i��n��\�����l����Ȃ�A�N����l�������������K�v�ł���B����ɕϑJ�����炩�ɂȂ邱�Ƃɂ���Đ��i�ɂ��Ă����y�ł���\�����w�E���ꂽ�B
�@�܂��P�Ȃ鐅���Ƃ̈Ⴂ�ɂ��ẮA���n������ɑ����̗v�f���Ƃ肠���A���r�ł��邱�Ƃ��q�ׂĂ����K�v�����w�E���ꂽ�B�����č���w�E���ꂽ�������ׂ�������܂ߍĐ�������K�v�����邱�Ƃ��w�E���ꂽ�B
�@�뉀�j�̗���ɂ��ẮA���ɓ������̎��@�뉀�ɂ��Ē��ڂ���K�v���w�E���ꂽ�B���X���ƒ뉀�����@�뉀����h���������̂ŁA����������ɉ�ɂ����鉀�r�̔������l���邫�������ɂȂ�̂ł́A�Ƃ����ӌ����������B
�@���̑��ɂ��l�X�ȓ_���w�E���ꂽ�B����͂������Q�l�ɂ���ɏڍׂȌ������K�v�ł���B
��W����@2004�N12��18���i�y�j
�M�ӈ�@�u�ɐ��ɂ����鋞�s�n�y�t��M�̎�e�ƓW�J�`��������𒆐S�Ƃ��ā`�v
�@����̕ł́A�����̍l�Î����̂����S���ɍL��ȕ��z��������A�u���s�n�y�t��M�v�����グ�A���݂܂ł̊w�j��U��Ԃ�A���Ɉɐ��̏o�y����ɂ��Č������������B
�@�����s�s�E���s�ŏo�y����y�t��M�͋��s�ߍx�Ő��Y���Ȃ���A�s�s���𒆐S�ɗ��ʂ��Ă����B����ɁA���s�ȊO�ɑS���e�n�̍L���n��ł́A�����̖͕퐶�Y�������Ȃ����A���s�n�y�t��M�̍L��ȕ��z���F�߂���B16���I��ɂ͐퍑�喼�̗̍���̖{���n�ɂ����Ėڗ����ďo�y����ق��A�ߔN�̌����ł͕��ƋV��Ƃ̊֘A�����w�E����Ă���B���������A���s�n�y�t��M�͕K���������s�ߍx�Ɍ��肳���̂łȂ��A�S���ɍL���W�J���邱�Ƃ���A�ݒn�̓y�퐶�Y�̕��݂͂̂Ȃ炸�A�����I�E�����I�Ȃ������ȂǑ��l�ȑ��ʂ��猟��������l�Î����Ƃ�����B
�@�ȏ�̂悤�ȁA�ߔN�̋��s�n�y�t��M�Ɋւ��錤�������܂��A�{�ł͈ɐ��̏o�y����ɂ��ĕ��͂������Ȃ����B���̌��ʁA�ڍׂȎ������肪�ł��鎑���͏��Ȃ����A��قɊ֘A������̂𒆐S��15���I�㔼�`16���I�O���̎��Ⴊ�������ƁA���z�̌�������A�L���͈͂ŕ��z���F�߂���鎭��Ȗk�̖k���n��ɑ��A������ȓ�̒��E�쐨�n��ł͖k�����֘A��Ղɂقڌ��肳���悤�ɒn��Ԃ̑��Ⴊ�F�߂���_�𖾂炩�ɂ����B�܂��A�ݒn�Y�̓y�t��M�Ƌ��s�n�y�t��M�Ƃ̔�r����A�k���n��ł͋��s�n�y�t��M�̉e�������ƍl�������Q��������̂ɑ��A���E�쐨�n��ł͂��������e�������Ȃ����Ƃ��m�F���A���z�̈Ⴂ�ɂ́A���n��ɂ����鋞�s�n�y�t��M�̎�e�̑��Ⴊ�w�i�ɂ��邱�Ƃ��w�E�����B
�@�������Ȃ���A�S���̌����������T�ς���ƁA�e�n�ŋ��s�n�y�t��M�̌������[�������邪�A�ǂ̗v�f�������āu���s�n�y�t��M�v�Ƃ���Ƃ����m�łƂ�����`�Â����\���Ȃ���Ă��Ȃ����ƂɋC�t���B��������A�����҂ɂ���āA�u���s�n�y�t��M�v�̊T�O�⑨���������قȂ�_�͔ۂ߂Ȃ��B�n���ł͂��邪�A�e�n��̍ݒn�n�y�t��M�̌����Ȍ�������A���s�n�y�t��M�𑊑Ή����A���ꂼ��̒n��ɂ����āA�����̈�Q�̏ڍׂȈʒu�t���������Ȃ���Ƃ��K�v�ł���B����������Ƃ̐ςݏd�˂ɂ���āA�����I�E�����I���ʂɂ܂œ��ݍ��A�X�̖L���Ȓn�摜���𖾂��邱�Ƃ��\�ƂȂ낤�B
��V����@2004�N11��20���i�y�j
�@�v���s�˖ؒ�����Ք��@��������̌��w

�@����̗��ł́A���@�������s���Ă���v���s�˖ؒ��̏���Ղ̔��@������������w�����B����Ղł͂Q�O�O�O�N�ɔ��@�������s���A�퐶���ォ�璆������܂ł̗l�X�Ȉ�\�E�╨����������Ă���B�����Ɍ����Č����Β����O������퍑���̉��~�n�Ɠ��H�A���H�������Č@�킳�ꂽ��K�͂Ȗx�i�ȉ��u��x�v�j���������Ă���B��x�ɂ��ẮA���c�B�����ɂ��V���P�Q�N�i1584�j�̌˖؏�U���ɂ�����A�H�ĕ��ɂ���Ēz���ꂽ�t��̈�\�ł͂Ȃ����Ƃ�����������Ă���B

�@���w���s�����̂͑�x�����p�ɓ�ɐ܂�A�J�ɗ����Ă��������ł���i�ʐ^�P�j�B���̕����ɂ͂���܂łɂ��x�ꂩ��s���ɓ��邽�߂̌Ռ�������̂ł͂Ƃ����z�肪�Ȃ���Ă���B���@�����ł��J����オ���Ă���ʘH���\���R�����m�F�i�ʐ^�Q�j���ꂽ�B�����̒ʘH���\�́u�t��v�ȑO�̂R���̉��~�n�i14�`16���I�j�ɑΉ����Ă��邱�ƁA�s���ւ̌Ռ����R�������������Ă��邱�Ƃ͖h���s���R�ł��邱�ƁA����܂ł̒����i��P�������X��j�ł� �ގ�����ʘH���\�����������ƂȂǂ���A�����͒�������̉��~�n�ɂƂ��Ȃ����̂ŁA�t��̌Ռ��ł���\���͒Ⴂ�̂ł͂Ȃ����ƍl����B�������ł��k�̒ʘH�t�߂ɂ͎��R�n�`�̋N���ɂ��킹�Ă��鉮�~�n�̈�\�Q�Ƃ͈قȂ芮�S�Ƀt���b�g�ɂ��ꂽ�e���X��̍핽�n�i�ʐ^�R�j������A����Ɋւ��Ă͕t��̌Ռ��֘A�̈�\�ɂȂ�\��������B����A�J�Ɍ����Ă̕����̔��@�ł͂��̕������ǂ̂悤�ɂȂ邩�𒍖ڂ������B �ގ�����ʘH���\�����������ƂȂǂ���A�����͒�������̉��~�n�ɂƂ��Ȃ����̂ŁA�t��̌Ռ��ł���\���͒Ⴂ�̂ł͂Ȃ����ƍl����B�������ł��k�̒ʘH�t�߂ɂ͎��R�n�`�̋N���ɂ��킹�Ă��鉮�~�n�̈�\�Q�Ƃ͈قȂ芮�S�Ƀt���b�g�ɂ��ꂽ�e���X��̍핽�n�i�ʐ^�R�j������A����Ɋւ��Ă͕t��̌Ռ��֘A�̈�\�ɂȂ�\��������B����A�J�Ɍ����Ă̕����̔��@�ł͂��̕������ǂ̂悤�ɂȂ邩�𒍖ڂ������B
�@���@�����͑�K�͂ɓW�J���Ă���A�k�[���ł͒����O���̌@����������a �A�ʘH��\���m�F����Ă����B���̕����̒ʘH�ł͔g���\�������́i�ʐ^�S�j������A�J�����n�ɏオ�邽�߂̒ʘH�������������ɕt�����Ă������Ƃ�����ł���B�Õ�����`���a�������A���炽�߂đ��Ղł��邱�Ƃ��m�F������ꂽ�B �A�ʘH��\���m�F����Ă����B���̕����̒ʘH�ł͔g���\�������́i�ʐ^�S�j������A�J�����n�ɏオ�邽�߂̒ʘH�������������ɕt�����Ă������Ƃ�����ł���B�Õ�����`���a�������A���炽�߂đ��Ղł��邱�Ƃ��m�F������ꂽ�B
�@
���w�ɂ������Ă͋v���s����ψ���̒҂���ɂ͋x���ł���ɂ�������炸�����J�ɑΉ����Ă��������܂����B�����\���グ�܂��B
�@�@�@�@�i���Ӂ@�|�c�����j
�˖ؒn��Ɋ֘A����j���ɂ���
�@�ؑ��������j�������i�O�d��w�j�Ƃ��̕���Ɓi�v���s����ψ���U�w�K�ہj�̐��ʂ������A����ՂȂ�тɌ˖ؒn�挩�w�̕X���͂���ƂƂ��ɁA���ᔻ�������������Ƃ����B�Ȃ��A���������̐��ʂ����J����ׂ����̍�Ƃ͌��݂��p�����Ă���B
�@���āA����Ղ̃V���|�W�E���͎O�d��w����ÁA�v���s����Âɂ��v�Q�s���Ă���B���̃V���|�W�E���ŕ��ꂽ���e�̓��A�l�Êw�i�P��ځA�Q��ځj�A��s�j�i�P��ځj�̕�����Ղ𒆐S�ɐ��������̂ł������B�������Ȃ���A�����j�w�����ɐ������ł́A�j���I����ؑ��n��̌��������S�ƂȂ����Ղ���я���Ղ̂���˖ؒn��̈ʒu�Â����ϋɓI�ɍs��ꂽ�Ƃ͌�����B�V���|�W�E���W�҂ɂ��˖ؒn��ւ̐ϋɓI���y���s���ƂȂ��Ă���Ƃ����悤�B�����ŁA�ؑ��n��̋ߐ��E�ߑ�j���Ɍ�������j�F���A�n��F���𒊏o�A�z�A����̌����̑�����������낤�Ƃ����B
�@���݂̌����́A��P��̃V���|�W�E���̌��ʂW���������w�O�d���v���s����ՂɊւ��鑍�������x�ɑ�\����Ă���B���̕��ɉ�����˖ؒn��̎戵�Ɋւ�����_�Ƃ��ẮA�����������p���Ă�����̂̂��̏������F���ɑ����̍������݂���_����������B�����ŁA�˖ؒn��̒n�А}�i�v���s���������j�̑S�B�e���s���i�v���s����ψ���U�w�K�ۂɂ��ؑ��������j�������̕���Ƃ̈�Ƃ��āj�A���y���玑���E�n���i�˖؏��w�Z�A�I�t���w�Z�����j�E�����̎j�ȂǂƑΏƂ������B���ʂ͈ȉ��̒ʂ�ł���B
�@ �����u����Ղ̕t�镔���v�Ƃ���Ă��镔���̎����́u���_���v�ł���A���u�H��v�ł͂Ȃ��B�u���_���v�͌��́u���M�v�u�쌴�c�v�u���v�Ƃ������ł������B�u���_���v�ɂ͌˖̑呠���̈ړ]�`��������i�w�v���s�j�x���j�A�u�呠���R�v�Ƃ���y�n���u���_���v�̒��ɂ������i�w�v���s�j�x���j�B�呠���͖ؑ����Ɋւ���R�����L���āi�w���������W�x�w����s�j�x�����j�������A�������̒n���ނɂ͖ؑ����̗R���A�ړ]�`���Ƃ��ɋL����Ă��Ȃ��B
�A�˖ؒn��ɂ�����@�ȊO�̎��@�Ɋւ���`���́A�����b���ɐ����Ɍ��Ă��Ƃ�����P�����i�w�{�����m�`�x�j�i���݂͒c�n�̖��Ƃ��Ďc��A���u�l�ˁv�u��v�j�A�������̓���B���P�����͓����̎��@�����c���ɍ]�˖��܂ő��݂��A�����ɂ͓��F����Ƃ��Ďg�p����Ă����i�I�t���w�Z�������y���玑���j�B
�B�ߑ�ɉ����ẮA�˖̎��u��v�i�_�o�p���̎搅���k���j�͉_�o��㗬����M�^�ɂ���đ�����d�Y�̗��g�ꏊ�ƂȂ��Ă����B�������A�M�^�͔_�Ɨp�����K�v�ȋG�߂ɂ͕s�\�ł������i�˖؏��w�Z�������y���玑���j�i���Ȃ݂ɖؑ��n��̏M�^�ɂ͋G�ߐ��͂Ȃ��悤�ł���j�B
�C�˖̏����̗R�������A�쌴�c�s�Y�ƕ����i�v���s�}���ّ��j�̒��ɑ��݂��Ă����B
�@�ȏ�̎������w�E�ł������A�����̖w�ǂ́A�ߑ�̗��j�F���E�n��F�����畂���яオ�������ł���B�������������̋{�R�鏄�����A�{�R�邪���͖ؑ����̏o�邾�����Ƃ����n���Ɋ�Â��F���ւ̋^�₪�����ꂽ���A����̍�ƂŖ��炩�ɂ������j�F���𑊑Ή����퍑�E�D�L���̎����ւ��܂��Ƃ�����̉ۑ�ƍl������B
�@�������q���_�Ћ����ł����Ȃ�����������ɕ⑫�������܂����B
�@�@�@�i���Ӂ@���c���r�j
��U����@2004�N10��30���i�y�j
��}��u�u�u���ߐ��ڍs���ɂ�����ɐ��_�{�����O���R�c�̓s�s�I�l�����߂����ā`���ɎR�c�O���n��E�O�{�Ƃ̊W���Ǝ��Ԃ��厲�Ƃ��ā`�v
�@�{�ł́A���ߐ��ڍs���̈ɐ��_�{�O�{�����O���R�c�̓s�s�I�l���ɂ��āA���ɓ��Y���ɓs�s�I�`��������ꂽ�ƈʒu�Â�����R�c�̊O�����̒n��\���̎��Ԃ�_�����B���ɕ҂ł��鎄�́A�R�c�O�����ł��鐨�c�여����͍̉苽��퍑��������}���ɐ������ꂽ���Y�n��̏��i���ʂ́w�h�x�I���݂Ƃ��ʒu�Â��A�͍肪�ɐ��_�{�O�{����{���͂��߁A���̒����O���ł���R�c�i�ܒ��S���j��F���A�����Ĉɐ��_�{�O�`�ł���喩���ɂ����Z�ƕ����̖ʂʼne���͂�^���Ă��邱�Ƃ��܂��w�E�����B���̏�ŁA�͍�ɑ��݂������K�ƕĂ̓��Y�n�擝��̑���ł���w�͍葊��x����ɁA�喩��͍�ŎR�c��F�����̓��Y�n��̓������������i�ȉݕ��̏s�ʂ��s���Ă������Ԃ���A���̍s���̂��`�p�n��̋��Z�E�W�@�\�Ƃ��ĕ]�����A���Y���̎R�c�͂��̂悤�ȍ`�p�n��̋@�\���܂߂Ēn��\������}���Ă������Ƃ������������Ƃ�����i�w��R�V����{�Õ����w����x2004�N10��3�����}�g��w�j�B
�@�������A�ēx���̕��e���ᖡ�������ʁA�ߔN���Y�n��ł����������݂��Ă���l�I���ʂ���̒n��\���̕`�ʂ̎��_����L�̌����ł͎�|�̈Ⴂ������i�ݕ��E���Z�_��j���_����̍s�_�j������g�ݍ��߂��Ă͂��炸�A�n��Z���̋�̑����s���m�ł���Ƃ���������������ɒv�����B���������Ė{�ł́A���ߐ��ڍs���̓��Y�n��ɐl�I���ʂ���̒n��\�������݂��Ă��邩�ǂ�����n��Ԃ̐l�I�l�b�g���[�N�Ƃ������_�Ō����邱�Ƃ����݂��B���̍ۓ��ɁA���ߐ��ڍs�����Y�n��̐��^�_�◬�ʘ_��W�J���邽�ߏ]�����d�v������Ă����ɐ��M�̓`���҂ł���A���F���t�����ċƎ҂ŏ��l�I���ʂ����Ƃ�����ɐ���t�̕����ʂł̎��Ԃɒ��ӂ����B
�@�����̈ɐ���t�̗L�͒U�߂͐퍑�����w�ł��������A�ޓ����푈���Ɉɐ���t�폟�F�����̏@���I���ʈȊO�Ɋ��҂��Ă������Ƃ̈�ɕ��ƕĂȂǂ̌R�������̒��B������B���̊��҂�����l�ɖ؉�������d���Ȃ�퍑�����������B�ނ͓����̐w�ہA�t�U�W�̂���R�c�O�����ł�����ɋ��Z�����O�{��t�ł���k�ĕ���v�ɑ喩�ł̕��ƕĂ̒��B���˗����喩�N��ɖk�Ƃ��|�������Ƃ����A�喩�Ƃ̐l�I�l�b�g���[�N�����҂������ƕĒ��B��k�ƂɈ˗��������Ƃ��������B�����A�k�Ƃ͎R�c�̏��ƒ��S�n��Œ��S���ł��锪���s��ɋ��Z�����O���N��Ƃ̖��ƕ��������Ƃ̈�Ղ��p�����Ă����B���̕����Ƃ́A�ȑO���喩�̗L�͏��l�k��Y���q�ƂƐe�ʊW�ɂ���A���̊W�𗘗p���ĉ��D��p���ĒU�����蓙�̌o�ϊ�����W�J���Ă����B�����Ƃ̈�Ղ��p�������k�Ƃ͏�L�̖؉����̂悤�ȃj�[�Y�ɂ́A�����Ƃ����ɗL���Ă����l�I�l�b�g���[�N�𗘗p���邱�Ƃł���ɑΉ��������̂��̂Ƒz��ł��悤�B�܂�A�k�Ƃ̕����ƌp���̔w��ɂ͎���̉Ƌ؋����̈Ӗ������̑��ɕ����Ƃ��l�����Ă����喩���l�Ƃ̐l�I�l�b�g���[�N�̋z���̈Ӗ��������������Ƒz��ł���B
�@���������āA���̎��Ⴉ��]������m����w�ɐ���t�����D��x�Ƃ����P���Ȑ}���Ƃ͈قȂ�l�I�Ȓn��\�������݂��A���̐l�I�l�b�g���[�N�̌`���Ƌz�����Ђ��Ă͎R�c���ӕ��i�喩�j�E�R�c�O�����i�j�E�R�c���S���i�����s��j�̒n��ԃl�b�g���[�N�̌`���Ƌ����̈���ł���Ǝw�E�ł���B����ɓ����A�D�c�M�Y�͓����ɓ��ʕĂ�ԕʕĂۂ��Ă��邪�A���̔��o�̑����͉͍�ōs���Ă���A�M�Y�́w�튯�l�x�I���݂ł���k�ĕ��Ƃ͂����̒�����Ə�����A���o�̍ۂɂ͎�̓I�Ɋ֗^����ȂǁA�n����ł̓����I�n�ʂ��ێ����Ă����B�܂��k�ƌl����M�Y�ւ̋��K�̎n���̍ۂɂ��͍�ݏZ���l����݂����Ă���B���̂悤�ɐD�c�M�Y�̂悤�Ȍ����͓͂̂悤�ȎR�c�O���n���l�I�ɏ������A�����ɓ��݂���l�I�l�b�g���[�N���z�������ʂ����������Ă����̂ł���B
�@�܂�A�퍑�����ɓs�s�I�Ɍ`�������R�c�O���n��ł�����i��V���j�Ɖ͍�͑��݂Ől�I�ȃl�b�g���[�N�łȂ����Ă���A�Ђ��Ă͂��ꂪ�n�擯�m�̃l�b�g���[�N�Ƃ��Ĕ��W���Ă���Ƃ����A���q�̑喩�Ƃ̐l�I�l�b�g���[�N�����l������ƎR�c���ӕ��i�喩�j�E�R�c�O�����i�͍�E�j�E�R�c���S���i�����s��j�͐l�I�l�b�g���[�N����Ēn��Ԍ������͂����Ă����Ƃ�����̂ł���B���̂悤�Ȑl�I�l�b�g���[�N�͑��ɂ��ޗႪ���o�ł��邱�Ƃ���i�̌�މƂƉ͍�̉����^�O�ƂƔ����s��̕����䉖�ĉƁA�͍�̑��c�ƂƊ╣�̋v�ۑq�ƂȂǁj�A�e�����ꂼ��̗̈�̓Ɨ����������Ƃ����R�c�ɂ����Ă͂����̒n����q���邽�߂̑傫�Ȓn��\���̗v�f�Ƃ��Ă��ꂪ���݂��Ă���ƋK��ł��悤�B
�@���������āA���̒n��ɓ��݂���n��Ԃ̐l�I�l�b�g���[�N�͓��Y�n��̒n������̈�Ƃ��Ēł���̂ł���B��������̂悤�ȓ��Y�n��̐l�I�l�b�g���[�N�̋�̗������w���o���A���Y�n��̒n��\���̈�Ƃ��Ēł���悤�ɐS���������ƍl����B���̍ہA�n����̗L�͎ҁi�ɐ���t����D�Ǝғ��j�̑��`�ԁi���Ɍ����͂Ƃ̊ւ��j�ɂ��Ē��ӂ��Ă����K�v������B
��T����i�������錩�w��j�@2004�N�X��18���i�y�j
����F�|�c����

�@��������́A�V��8�N�i1580�j�ɐD�c�M���̎��j�M�Y�ɂ���č���̒n�ɒz���ꂽ��Ղł���B�V��12�N�i1584�j�̗���̂̂��������������邵�A�V��16�N�i1588�j�Ɏ����������Ɉڂ�܂Ŗ{���Ƃ��Ă����B����܂łɂ��A�������T���A�O�n�r��Y���E���R�����E���c�N�玁�̘_�l�����邪�A����͍ŐV�̍גJ����ق��u�ɐ�����������Ƃ��̏鉺�̌i�ρv�i�w���Ձx�T���@�c�{�ّ�w�l�Êw������@2003�N�j���e�L�X�g�ɁA��������ՂƂ��̏鉺�̌��w���s�����B
��ʘH�̓����@�������́A�ɐ��p�ɖʂ����l���ɗ��n���A�Ñ㖖����u�ۑ��v���v�i�ق����сj�ȂǂƂ݂��A�ɐ��Q�{�Ɍ������r���ɎO�n��̓n����̈�ł������B�D�L���ɂ́A����ɐ��ɂ��������ɐ��X������������ł���B���̃��[�g�t�߂ɂ́u�ޖؒ��v�E�u�k�s��v�E�u�{���v�E�u�����v�E�u��m���i�����̂܂��j�v�ȂǂƂ����n�����c��B���������̕����͐V�c�J���⍑���H���ɂ�艝���̎p�͗��߂Ă��Ȃ��B
��s�����@�������̒��ŁA�u��s�v�ƍl�����Ă���̂́A�u��̍��v�̓V���ՂƂ��̎��ӁA�u�� �V���v�E�u�a���v�̕����ł���B�V���͖{�ۂ̒[�ŁA�����ɂ͊C�ɒ���o���Ă����Ɛ��肳��Ă���B�������V���Ƃ����Ă��A�Ί_�͊��ɂȂ��A���Ђ�y��Ђ��U������B�u��̍��v���܂ޖ{�ە����ł́A�X���O�͕\�ʍ̏W����Ă���B�܂��k�쒆�ɂ͈�˂�I���݂��������Ƃ�����B �V���v�E�u�a���v�̕����ł���B�V���͖{�ۂ̒[�ŁA�����ɂ͊C�ɒ���o���Ă����Ɛ��肳��Ă���B�������V���Ƃ����Ă��A�Ί_�͊��ɂȂ��A���Ђ�y��Ђ��U������B�u��̍��v���܂ޖ{�ە����ł́A�X���O�͕\�ʍ̏W����Ă���B�܂��k�쒆�ɂ͈�˂�I���݂��������Ƃ�����B
�@�u�۔V���v�ɂ́A�u�������~�v�Ƃ����ꏊ������B���̕t�߂ɂ͋͂��ɓ��x�̍��Ղ��c���Ă���B�܂��אڂ��āu���_�_�АՁv�����݂���B�܂��A�u�a���v�ł͕����炵���������i�A�R�r�LA�̊���l����̐Η���o�y�������Ƃ�����B�@
�u�鉺�v�����@�u��̍��v�E�u�۔V���v�E�u�a���v�����Ɍ������u�x���v���߂���������ɂ́A�u�b�����v�E�u�������v�E�u�k���v�E�u�����v�Ȃǂ̒���炵���n��������B���̕t�߂ɂ͕�n�⎛�@�����݂����Ƃ̂��Ƃł���B�܂��A�k�ɂ́u�������v������B�u�������v�ɂ́u�������~�v�Ƃ����镔��������B�����͂���܂ł̌����҂������u�M���v��z�肵�Ă���u�h���T�v�Ƃ������n�ɂ��ʂ��Ă���B�גJ���̑z��ł͂��́u�M���v�����Ȃ�傫���ݒ肳��Ă���B���̂�����͊m�F���K�v�ł���B�܂����̕t�߂ł͖k�����Ɗ֘A����Ǝv����A�H��̓��������������o�y���Ă���B
����Y�@�u�������v����x�i�l��f����j��������������Y�ł���B���̖x�͌c��2�N3��21���t���̉F��v�E�q�发��Łu�䎛�O�x�v�Ƃ��ďo�Ă���x�ł���B���̖x�ł͉͐���C���Ƃ��\�肳��Ă���A�ی�E�ۑ����ۑ�ƂȂ��Ă���B����Y�ɂ͓�k�ɐ����̊X�H���̂���A�Z����̒n���������ɂ݂���B���̖k�[�ɂ͏�����_�Ђ�����B���̕����Œ��ڂ��ׂ��́A�_�Ђ�����Y�̒n���ɋK�����ꂸ�ɓ�k�����ɍ���Ă��邱�Ƃł���B�_�Ђ�������ɐ�s���đ��݂��Ă����\��������������̂Ȃ̂�������Ȃ��B
�@�ȏ�A�������̌��w���s�������A���W���ɂȂ��Ă�����̂́A���̕ۑ���Ԃ͋ɂ߂ėǍD�ł��邱�Ƃ��Ċm�F�ł����B�������Ȃ��璎�H����̊J���͐i��ł���A���}�ɕی�̎藧�Ă����K�v��������Ǝv����B���w��̓��e�ɂ��ẮA����w�K��ɂČ�������\��ł���B
��S����@2004�N�V��1�V���i�y�j
�R�ە����u�����s�s�����j�v
�@�P�X�T�O�N�ォ�猻�݂܂ł̓s�s�����j�A���ɍl�Êw�ɂ�����w�j�����グ���B
�@�]������w�E����Ă���悤�ɁA�����哱�ł��������̂��A�U�O�N��ɓ���ƍl�Êw�ł͍L�͈͂ɂ킽�蒆���s�s��Ղ̔��@���s���͂��߂����Ɓi���J�A���ː猬�A��ɕ{�Ȃǁj�B�V�O�N��ł́A�Ԗ�P�F���́u�s�s�I�ȏ�v�ɑ�\������A�̘_�ɂ��A����ȍ~���̒ƒZ���I�Ɍ��ѕt������̓I�E���ԓI�ȋ�ԂłȂ��c��Ȓ����s�s���o�������Ă��܂������̂́A�������̒����Ɍ�����悤�Ɉ�\�ʂ�w�ɒ��ڂ������@�_���m�����ꂽ���ƁB�W�O�N��͋�ԁ���̕��͂�ړ_�ɁA�����E�l�ÁE���z�̋����������n�߂��A�X�O�N��͂���W�p�����A�O��v���ɂ���āu�s�s�l�Êw�v���W�Ԃ����Ɏ��������ƁB�����ċߔN�ł͓s�s���ꎩ�̂̔c���Ɍ��肹���A���̂��Ƃɂ��s�s�ւ̃A�v���[�`������ɓn�邱�Ƃ��Ċm�F�����B
�@�w�j���T�ς���ƁA�����������[�߂�ꂽ�Ƃ͂����A���ʂ́u�����s�s�Ƃ͉����v�Ƃ�����`�����܂���������Ă��Ȃ����ƂɋC�t���B�X�̌����҂��X�̓s�s���������A���ꂼ��̕��@�_�œs�s�փA�v���[�`���邱�Ƃ�����ɖ��͓I�ȓs�s���������яオ���Ă���͎̂������B�����A�ʂ����ċ��ʂ���������[�߂邱�Ƃ��ł���̂��낤���Ƃ����f�p�ȋ^����������ɂ͂����Ȃ��B�s�тȖ₢�ɏI��邩������Ȃ����A����x�u�����s�s�Ƃ͉����v�Ƃ����������K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���B
���яG�u�����s�s�����̈ꎋ���\�x��S�R�c���𒆐S�Ɂ\�v
�@�{�ł́A��������ɁA�u�O���v�Ə̂��鋭�łȎ����g�D�̂��������ƂŒm���Ă���R�c�̒����`���ɂ��āA���ɉ��~�����𒆐S�Ɍ��������B���̌��ʁA�X����u���Áv�����ł͒Z���`�̍ג����n�����A�x���Ƃ�16���I�ȍ~�͕��ՓI�Ɍ`������Ă������Ƃ��w�E�����B�܂��A�R�c���ł́A�ꏊ�ɂ��n���ɒ�������������A���ł������s��ł́A���̓����������ł������B����͓y�n���p�ɂ�鍷�ƍl�����A�ɂ߂ēs�s�I�ȓ����ƌ�����B
�@���ʁA�R�c�𒆐S�Ɍ�����A��ɐ��n��œ����I�ȍȓ���Z���͉ߖ��Ȓ���ɂ͕s�����ł���A�R�c���{���A�_���I�ȏW������}���ɓs�s���������Ƃ������Ă���B���̂��Ƃ́A�y�n�����̒��ɂ������I�Ɍ���Ă���B
�@�Z���`���~����t���~�́u�O���~�v�Ɖ����邱�Ƃ͍���ł���A��w�Ɉʒu�����t���~�́A�����̎����n��A������܂ލL����M�Ȃǂ����邱�ƂŌ`�����ꂽ�ƍl����B���̌X���́A����16���I�ȍ~�́A�_��l���̐E���l�w���o���Ƃ����t�Ɍ����ł������B�܂��A�ނ�̐i�o�̔w�i�ɂ́A�P��I�Ȑ_�Œ����ɂ�镨���̗��ʂ�A�ɐ��M�̑�O���ɂ��Q�w�҂̑����Ȃǂ��������ƍl������B
��R����@2004�N�U��1�X���i�y�j
�R�c�Y�i�u�����ɐ����ɂ����鎞�O�̓W�J�v
�@����܂ł̒����s�s�Ɋւ��錤���ł́A�s�s�̗v���Ƃ��Č�ʂ̗v�Ղł��邱�Ƃ����ڂ���Ă���B���̂悤�ȏꏊ�͐l�X���W�Z���A�������L�߂�̂Ɍ����I�ŁA�L���l�̏Z�ޏꏊ�ł���A��̂��邱�Ƃ����҂ł����B���O�͈�Ոȗ��A���E�ÁE�s��E�h�Ȃǂɗ�������ċ������Ă���A���Ɏ��O�����݂�����Ƃ��āA�z�������ÁE�z�㒼�]�ÁE�������l�Ȃǂ��������Ă���B
�@�ɐ����������Ă݂�ƁA�w���O�ߋ����x�ɂ��ƁA�K���A�l���s�A���i�A���q�A�E�c�A���Z�ÁA���A���{��A�����A�R�c�ȂǂɎ��O�̓k���������Ƃ��m�F�ł���B�܂��A�w�V�s�O�\��c���E��C�s�L�x����́A���O�����Z�Â��甒�q�Y�܂ʼnב��M�ɏ���Ă����A��O�͗��H�K���Â܂ōs���Ă��邱�Ƃ��킩��B�V�s��l�͈ɐ��p�݂��M�ʼn�������Ƃ����������̂ł͂Ȃ����낤���B�ÁE���͂��܂��܂ȏ@�������݂��A�x���W�����A������킳���ꏊ�ł������B
���c�B���u�������Ղ̓s�s�v��v
�@�{�ł́A�������Ղ��c��16�N�i1611�j�������瓯���ɊJ�n�����ɉ���E�ɐ��×���s�̉��C�E���鉺�����݂̗��j�I�Ӌ`���������邱�Ƃ��ۑ�Ƃ����B
�@���ɂ��ẮA�ȉ��̓�_���w�E�����B
�@��s�{�I�ɉ��C���A�����̍U�����\�z����鐼���ɋȗւ��g�����Ė{�ۂƂ��A�䍂��30���[�g���Ƃ�����ꋉ�̍��Ί_��z�����B��s�i���{�ہj�̑����ɕύX���A����쑤�̓����̗����Ƃ���B
�A�鉺�����A�v�Q���̍�����s�쑤�̏���n��Ɉړ]�����āA�O�ؒ��Ƃ��ċÏk�����B
�@�Âɂ��Ă��A�ȉ��̓�_���w�E�����B
�@��s��k�����ɉ��C���A�����̍U���ɔ�����ƂƂ��ɁA�O�C�n�̈ɗ\������̎����Ȃǂ����p���A����߂ĒZ���Ԃɖ{�ۂ�O�s���g�������B
�A�鉺���Ɉɐ��X�������A�h�w�@�\�����������B�܂��ɉ�X�������邱�Ƃɂ���āA�Â������Ə�������ԗ��ʂ̌��ߓ_�ɂȂ����B
�@�����̍��Ղ́A����͖Ԃ��`�����邽�߂Ɍ��V�����i�V�������j�ɐϋɓI�Ɋ֗^�������A���̂̏�s�����̈�Ƃ����B�܂����ƒÂ��X���Œ��ڌ��Ԃ��ƂŁA�ɉꂩ�璆���ɐ��ɂ���Ԕ˗̂��̍��Ƃ��Ď������邱�Ƃ��߂������B�Ȃ��ڍׂɂ��ẮA�ْ��w���{���E�ߐ��ڍs���̒n��\���x�i�Z�q���[�A2000�N�j��V�́E��W�͂��Q�Ƃ��ꂽ���B
��Q����@2004�N�T��1�T���i�y�j
�|�c�����u������ՂƉ������ِՁv
�@�鎭�S�֒��厚�����s��́A��������ɗ鎭�S�E��ȌS�ɐ��͂����������l�A�֎��̗L�͂ȉƐb�ł���������̖{���ƍl�����Ă���B�~�n�̖k�̎R��ɂ́A���̒n��Ƃ��Ă͔�r�I�K�͂̑傫���R��ł��������Ղ�����A���̘[�̐_�����͉������ِ̊ՂƂ���Ă����B
�@�������A�_�������琼�ɖ�0.5km���ꂽ���u�s��v�ɂċߔN�A���@�������s���A15���I����16���I�̌@���������Ղ��ʂ̓y�t��M�ށE���Ղ��o�y�����B�M�҂͂��̐��ʂ����ƂɁA�ߐ��̒n���ށA�G�}�A�����̒n�А}�A�����╨�̎U�z�A�R��̏�ՂƂ̊W�Ȃǂ͂��A�������̊ق͎��u�s��v���ӂɂ������\�����������Ƃ��m�F�����B
�@�]���̌����ł́A�����̎l���ɂ͒�����ق�����A�~�n���ɂ͉Ɛb�̉��~����������ł���悤�Ȍi�ς��z�肳��Ă����B�������A������ՈȊO�̏�Փ`���n�ɂ͒n�\�ʂŌ������h���\�͂Ȃ��A�╨�̕��z���U�ݓI�ł���B�ނ��닌��a�X���ɉ����Ė~�n�̐����玚�u�b�胖��v�A���u�s��v�i�ِՑz��n�j�A�_�������ӂɏW�����W�J����悤�ȕ��ߓI�Ȍi�ς��Ȃ��Ă����\���������B
�T�R���u�ɐ��T�R��Ց�11�����@�����̎G������v
�@�T�R�s����ψ���ł́A���w�Z���z�ɔ����A�T�R���V�ېՂ̔��@������15�N8�����畽��16�N3���Ɏ��{�����B���̒����S���҂Ƃ��Ē����ߒ��Ŋ��������܂��܂ȓ_���q�ׂĂ݂����B
�@�܂��A�����܂ő����������ۖ�E��V�ۖk����ՂɁu�j��v���v�킹��j�p�H�@������ꂽ���Ƃ���A��̌`�Ƃ��Ċ��������Ƃ݂�ߐ���s�ɒ�������̎v�l���Ō�܂Ŏp���ꂽ�̂ł͂Ƃ̎v�������������B17���I���`19���I�O���ɂ킽��g�p���ꂽ�ƌ������^�p����\�̑��݂́A����܂ŏ�勏�Z��ƔF������Ă�����a���̋�ԍ\���̍Č����𔗂��邱�ƂƂȂ����B�������w�i�퍑���j�ɂ������x�E�y�ۂ���i�̋ȗ��i����25���E��k50���j��3.5���̐��y���s���u��V�ہv�̌`�����Ă��邱�Ƃ����������B�����A���̏�17���I���`18���I�㔼�ɂ����Ȃ�ꂽ���̂ł���A�w���ۏ�G�}�x�̐���i�K�ł͓�V�ۂ̑������Ƃ������ƂƂȂ�B����̒����ɂ�鑽���̒m���͋ߐ���s�ɑ��Ă��܂��܂Ȗ���N�ƂȂ�̂ł͂Ȃ����Ɗm�M���Ă���B
�@�ߐ��T�R��̎��͂��猆�o�������͂ȋ��S���͓V�����ɂ͐��������ƍl�����邪�A��ɐ�s�����b��F�E���a�Ȃǂ� ��\�Q�̑��݂���A16���I�������ɂ͂��ł�����̌`�������������Ƃ��c������Ă���B������u�s�s�I�Ȃ��́v�ƕ]�����邱�Ƃ�ے�͂��Ȃ����A�����s�s�u�T�R�v����ƂƂ��ɐD�L���Ɋ��������ߐ��鉺���u�T�R�v�ƂȂ�̂��A�ނ��늰�i�`�c��������������ł͂Ȃ��̂��Ƃ����_������������������K�v��Ɋ������B2006�N�ɂނ��āu�T�R�v���ӂ̒����W���̓��������킹�āu�鉺���T�R�v�������e�[�}�Ƃ��Č�����i�߂����B ��\�Q�̑��݂���A16���I�������ɂ͂��ł�����̌`�������������Ƃ��c������Ă���B������u�s�s�I�Ȃ��́v�ƕ]�����邱�Ƃ�ے�͂��Ȃ����A�����s�s�u�T�R�v����ƂƂ��ɐD�L���Ɋ��������ߐ��鉺���u�T�R�v�ƂȂ�̂��A�ނ��늰�i�`�c��������������ł͂Ȃ��̂��Ƃ����_������������������K�v��Ɋ������B2006�N�ɂނ��āu�T�R�v���ӂ̒����W���̓��������킹�āu�鉺���T�R�v�������e�[�}�Ƃ��Č�����i�߂����B
��P����@2004�N�S��17���i�y�j
�ɓ��T�́u���͎҂̋��_�Ǝx�z�̈�̊W�\�k�����̗̈�Ƌ��_�E���C�\�v
��������̑喼���_�i�u��쒬�v��u�퍑���鉺���v�j�́A�ߐ��鉺���ݏo���f�n���������u�s�s�v�Ƃ��Ċ�{�I�ɕ]������Ă���B�������A�喼�̋��_�A���邢�͑喼���̂��̂��A���̗̈�₻�̒n��̈�\���v�f�ł���A���̂Ȃ��ő��Ή������Ƃ��K�v�ł���B���ł́A�k�����Ƃ��̋��_���C�i�O�d����u�S�������j��f�ނƂ����B
�@�܂��A���C�̋�ԗ��p�������B���C�̋�Ԃ͋ɂ߂Č���I�ł��邪�A�����͖k�����̊֗^�ɔZ�W�������A�V��悪���ߓI�Ɍ������Ă���ƌ����B���ɁA�k�����̌�ʘH�x�z�Ə��l�ȂǂƂ̊W�������B�k�����̌�ʘH�x�z�́A15���I�㔼��ȍ~�A���ȗ̈���z�������I�Ȏx�z��������B16���I��ɂ́A��ʘH�x�z�����ɍۂ��ēƎ��́u���V���v��L���Ă����B�܂��A16���I�㔼�̑��C�ɂ́A�ɐ��{�X�������ݏ��ɑ��鏤�ƓI���S�͂��z�肳�����̂́A���������ۂ���n��̋��S�͂͊O�{��O�R�c�ɂ͉����y�Ȃ����Ƃ��m�F�����B
�@�ȏ�̌�������A�k����������v�f�Ƃ���n��\���̒��ŁA���C�ɂ͓Ǝ��̋@�\��������Ă��邪�A����͌o�ϓI�����܂߂�A��ΓI�D�ʂȈʒu�ł͂Ȃ��B���C�̕��ߓI��ԍ\���́A�����̒n��\���̒��őI�������A���邢�͑I��������Ȃ������������Ă���A���ׂĂ̑喼���_���u�s�s�v���u������Ƃ͌����Ȃ��B�n���ɂ����鐭���I���_��]������ۂɂ́A�����̒n��\���ɑ��镪�͂��K�{�ł���ƍl������B
�}�䌫���u������ِՂƎs��n���v
�@�����s�s������O�d���i���j�ł͏]������s�s�Ƃ���Ă�����́A�s�s�I�ȏ�ł���\�����w�E����Ă�����̂��E���Ή����A�O�d���Ƃ����n��̂Ȃ��œs�s�����Č�������Ƃ��������Ō������i�߂��悤�Ƃ��Ă���ƕM�҂͗������Ă���B
�@�����������ŎO�d�����ɂ����Ē����s�s�Ƃ���Ă����K������Z�ÁA�R�c�B�喩�Ȃǂ̌ʂ̌������[�������ׂ��ł���Ɠ����ɂ����𑊑Ή������邽�߂ɂ��A�s�s�I�v�f���܂ޏ�A�n�_�̌ʌ����̒~�ς��K�v�ƍl����B
�@�M�҂͂��Ĉɐ������ɂ�����u�s�v�n���̏W�������݁A���̌��ʍł������F�߂���̂�24�ӏ�����u�s��v�n���ł���A���̑����͍��l�̎�A�Ȃ��ł��L�͍��l�̏�ِՂƂ����ꏊ�ɋ߂��ꏊ�̈ʒu���邱�Ƃ��킩�����B�s�E�s��͓s�s���\������v�f�Ƃ��ė�������Ă������Ƃ���A�O�d�����ɂ�����s��n���̕��͂�ʂ��āA���ь����Y���ɑ�\�����悤�ȗ��j�n���I��@�ɂ�錤����K�p���A�������T���̋��l�Ǝs���ꌳ����������������p���A������ِ�+�s��n�����ǒn�I�Ȓ��S�n���s�s�I��Ƃ��Ă̋@�\��L���Ă����\��������̂ł͂Ȃ����Ƃ����������B
�@���_�̒��ł́A���R�̂��ƂȂ���A���{�I�ɒn���݂̂ł͎��Ԏ�������ł��Ȃ��Ƃ�������A������قƂ̊֘A�����������n���Ƃ��ė�������ׂ��ł͂Ȃ����Ƃ̎w�E���ِՂƂ̊֘A��������ʘH�⎛�ЂƂ̊֘A��������ɓ���ł͂ǂ����Ƃ��������w�E�����B�w�E�̂Ƃ��荪�{�I�Ɏ��Ԏ�����ł��Ȃ��s��n�����������邱�Ƃ������s�s���������邽�߂̎����ƂȂ肤�邩�Ƃ����ۑ肪����B�j���Ɍ�����s��E�s�̌����A���z�����̎��{�ɂ�蓖�Y�n�̎��������i�邱�Ƃ�A�n�А}�⌟�n���Ȃǂ��������A���������ςݏd�˂���X�̎���ɂ��Ďs��n���̈Ӗ�����������K�v������ƒɊ������B
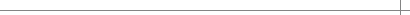 |
